どうも、あきです!
今回は、
「良い商品なのに売れない」売れる商品に必要な11の秘密について解説します。
「良い商品なのに売れない」…このタイトルを見て、ドキッとした方も多いかもしれません。
でも実は、これは私自身もかつてずっと悩んでいたことなんです。
✔ 頑張って作った商品が売れない
✔ SNSも毎日投稿してるのに反応が薄い
✔ いいサービスだと信じてるのに、それが全然伝わらない…
こう感じたこと、ありませんか?
でも、そのままにしておくと、どんなに良い商品でも埋もれてしまいます。
価格で比べられて、値下げしないと売れない…そんな悪循環にハマってしまいます。
今回の記事では、売れない原因の正体と、それを抜け出すために必要な「価値が自然に伝わるマーケティング設計」について、11のセクションに分けて丁寧に解説していきます。
実際に私もこの考え方を取り入れたことで、
無理なセールスをしなくても「この商品が欲しい」と言われるようになりました。
マーケティングって、テクニックではなく「伝え方と理解の設計」です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
今回の記事の動画はこちら↓チャンネル登録して効率的にマーケティングを一緒に学びましょう!
動画の方が記事よりも「例え」を多く入れて話しているので、理解しやすいと思います。
【セクション1】なぜ「良い商品」なのに売れないのか?
「良い商品を作れば売れる」は、もう通用しない
まず最初に伝えたいのは、「良い商品を作れば自然と売れる」という考え方は、残念ながらもう通用しない時代に来ているということです。
例え、品質が高くても、デザインが良くても、価格が手頃でも知られていない商品は、存在していないのと同じです。
心理学ではこれを単純接触効果(ザイアンス効果)とも呼ばれていますが、人は、繰り返し目にするものに好意を持ちやすくなる傾向があります。
つまり、「見込み客の心の中にあなたの商品やサービスが存在しているかどうか」「第一想起というポジション」が取れているのかで、結果が大きく変わります。
「価値が伝わらない」投稿の共通点
私がこれまでマーケティング支援で関わってきた中でも、地方のカフェや小規模店舗、個人事業主さんに共通して見られるのが、「発信しているのに反応がない」という悩みです。
投稿内容を見てみると、たとえばこうです。
「今日のパンです」
「新商品が焼き上がりました!」
情報は確かに伝わっているけれど、大事な「価値」が全く伝わってこないんです。
人が求めているのは「パンそのもの」ではなく、「そのパンを食べることで得られる幸せ」です。
「体験」にフォーカスするだけで、伝わり方が変わる
例えば、こう変えてみましょう。
「忙しい朝に、3分で幸せになれる焼き立てクロワッサン」この一文だけで、映像的に情景が浮かびますよね。
こうした感情に訴える言葉が、人の購買スイッチを押します。
行動経済学で見る「売れない理由」
行動経済学の観点から見ると、人は合理的にではなく、感情的に購買を決めます。
性能や機能の優秀さではなく、「自分の生活にどんな良い変化があるか」で判断する。
だからこそ
「この商品がどれほどすごいか」を語るよりも、
「この商品を手にしたお客様がどう変わるか」を語る方が圧倒的に心に刺さるのです。
「人は商品を買わない、変化を買う」
売れない原因の多くは「商品」ではなく「伝え方」です。
人は商品そのものを買うのではなく、「自分が得る変化」を買っています。
「パン」ではなく「朝の幸福」
「英会話」ではなく「海外旅行で自信を持てる自分」
「コンサル」ではなく「理想の未来を実現する力」
つまり、マーケティングの第一歩は、商品ではなく変化を伝えることです。
パッケージを変えるだけでヒットした事例
現場でもよくある話ですが、まったく売れていなかった商品が、
中身を変えずにパッケージとコピーだけでヒットしたという例は山ほどあります。
例えば、
「疲労回復ドリンク」→「午後の集中力を取り戻す一本」これだけで売れ行きが何倍にも伸びた企業もあるほどです。
他にも、「鼻セレブ」もともと「ネピア モイスチャーティシュ」という地味な商品名と目立たないデザインで販売されていた時期は、売上が伸び悩んでいました。
しかし、デザインと鼻セレブというキャッチコピーにして売上を10倍にしました。
まとめ(セクション1)
- 売れない理由は「商品力」ではなく「伝え方」。
- 人は機能ではなく、「変化」「感情」「未来」を買う生き物です。
- まずは「この商品でお客様がどう変わるのか」を明確にしてみましょう。
【セクション2】売れない構造を作ってしまう3つの落とし穴
ここからは、なぜ多くの人が「良い商品なのに売れない」という状況に陥ってしまうのか?
その構造的な原因を、3つの視点から掘り下げていきます。
この章は特に重要です。
なぜなら、あなたがどれほど努力しても「構造が間違っている」状態では、その努力のほとんどが空回りしてしまうからです。
落とし穴①「全部伝えたい」症候群
最もよく見られるパターンが、情報の詰め込みすぎです。
SNSも、LP(ランディングページ)も、広告も全部やります。
ターゲットも広く、メッセージも多い。
一見「やる気がある」ように見えるんですが、実はこれが大きな罠となっています。
心理学では「選択のパラドックス」と呼ばれています。
選択肢が多すぎると、人は混乱し、最終的に「選ばない」という行動を取ります。
たとえば、あるデザイン事務所のサイトで「ロゴも作れる、広告も出せる、SNS運用も代行可能、ウェブ制作もOK」と書かれていたら、結局「何が得意なの?」と分からなくなってしまいますよね。
一方で、「ブランディング特化で売れるデザインを作る」という一文だけであれば、
「この人はブランドづくりのプロなんだな」と明確に伝わります。
このように、削る勇気こそが、伝わるマーケティングの第一歩なんです。
実はこれは私も意識してないと陥りがちです。
あれもこれも伝えたい気持ちが強い方は特に要注意です。
私の場合LPでは全てごっちゃにして何でもできますよ!と説明しています。(概要欄にLP貼っておきます!)
ただ、YouTube動画を見てもらえればわかるのですが、広告の動画には広告の商品しか紹介しない!SEOの動画にはSEOの商品しか紹介しないというように価値提供の際は、ちゃんとあれもこれも紹介しないで、商品を分けて考えるという戦略を取っています。
YouTubeにおいては、これでお問い合わせから契約まで取れているので、問題ないと考えています。
ただし、広告でLPを回す場合は、価値提供ができていない状態でLPをお客様にいきなり見せるので、今のこのごっちゃのLPでは通用しないと思います。
その時は、この全部伝えたい症候群を治したLPを別途作る必要があります。
つまり、前提条件YouTubeからの集客なのか?広告からなのか?これらによっても戦略は変わってきます。
落とし穴②「機能説明だけ」になってしまう
2つ目の落とし穴は、サービスの特徴ばかりを語ってしまうことです。
あなたの商品説明に「最新技術を使用」「丁寧なサポート付き」と書かれていませんか?
これらは悪くないんですが、実はお客様はそこにあまり興味を持っていません。
お客様が気にしているのは、「それによって自分がどう変われるか」です。
マーケティングの世界ではよく「WIIFM(What’s In It For Me?)」という言葉が使われます。
つまり、「それって私にとってどんな得があるの?」という視点です。
たとえば、美容室で「カットが上手い」と言うよりも、「朝のセットが3分で終わる」と伝えた方が響きます。
機能ではなく、変化を語る。これだけで、伝わり方が180度変わります。
落とし穴③「比較の中に埋もれてしまう」
3つ目の落とし穴は、他社との比較に巻き込まれてしまう構造です。
あなたの商品が「どこでも買える」「誰でもできる」ように見えると、
お客様は「価格」でしか判断できません。
これは行動経済学でいう「ヒューリスティック思考」人は複雑な判断を避け、分かりやすい基準(価格・数字)で選ぶ傾向があります。
だからこそ、「安さ」ではなく「選ばれる理由」を作る必要があります。
よくあるケース
私が支援してきた中でも、特によく見られるのがコーチングやカウンセリングなどの無形サービスです。
多くの方が、「自分を変えたい」「成長したい」という思いでサービスを提供していますが、発信が抽象的すぎて「結局何をしてくれるのか」が分からないんです。
たとえば、「自己成長をサポートします」という表現では、それがカウンセリングなのか、ビジネス支援なのか、分かりません。
しかし、そこを「自分を責めるクセから解放される3ヶ月プログラム」と変えた瞬間、伝わるイメージが劇的に変わります。
数字ではなく、変化が明確になった瞬間に、お客様の理解が深まり、申し込みが増える。
この構造はどんな業種でも共通しています。
情報は「多いほど伝わる」のではなく「焦点で伝わる」
ここで強調したいのが、「情報の量」と「伝わりやすさ」は比例しないということ。
むしろ逆です。
本当に刺さるメッセージというのは、「多くを語る」よりも「深く刺さる一言」です。
たとえば
- ❌「幅広くサポートします」
- ✅「1ヶ月であなたの広告費を半分に」
たったこれだけで印象がまるで違いますよね。
これは焦点の力です。
情報を削る勇気と、絞る設計
情報を削るというのは、「伝えたいことを減らす」のではなく、「伝わるために磨く」ということです。
例えば、カメラのピントを合わせるように、「誰に」「何を」「どんな変化で」届けるのかを一つに絞る。
マーケティングで結果を出している人ほど、実はやっていることがシンプルです。
複雑に見える戦略の裏には、明確な「焦点」があります。
まとめ(セクション2)
- 売れない構造は「伝えすぎ」「説明しすぎ」「比較されすぎ」から生まれる。
- 解決策は、情報を削り、焦点を絞り、変化を伝えること。
- 「多くを語る」よりも、「深く刺さる一言」を磨こう。
【セクション3】売れる商品に共通する「顧客視点の原則」
ここまでで、「売れない構造」には3つの共通した落とし穴があるとお話ししました。
つまり、伝え方・焦点・比較構造がズレていると、どんなに良い商品でも選ばれない。
では逆に、「売れる商品」には何があるのか?
その答えが、顧客視点の原則です。
人は「感情で動き、理性で正当化する」
ノーベル賞を受賞した行動経済学者、ダニエル・カーネマンはこう語っています。
「人は感情で判断し、理性で正当化する。」
つまり、買うかどうかの最初の判断は「心」で決まっている。
そして購入後に、「自分の判断は正しかった」と理屈を探します。
たとえば、あなたが少し高い服を買ったとき、「生地がいいから長く着られる」と理由をつけますよね。
でも本音は、「着たときに気分が上がる」「自信が持てる」そうした感情が動機だったはずです。
「理屈」より「情景」を描けるかどうか
人の心を動かすのは、数字や機能よりも「情景」です。
例えば、フィットネス業界でよく見られる例があります。
「筋肉がつきます」では人は動きません。
しかし、「3ヶ月後、鏡の前で自信を持ってTシャツを着られるようになります」
と伝えると、感情が動きます。
購買行動を動かすのは、「数字」ではなく「未来のイメージ」
ここを設計できる人が、売れる人です。
顧客視点を鍛える3つのステップ
顧客視点を持つことは、単なる「ペルソナ設定」ではありません。
多くの人が「理想の顧客像」を頭の中で作りますが、実際のマーケティング現場ではそれだけでは不十分です。
顧客視点を鍛えるには、次の3ステップが有効です。
1️⃣ お客様の悩みを10個書き出す
「夜眠れない」「お金の不安がある」「発信が怖い」など、リアルな悩みを想像します。
2️⃣ その悩みに対して、商品が与える変化を10個書く
例えば、 「夜寝れない」→ 夜ぐっすり眠れるようになり、朝スッキリ目覚められる
「お金の不安がある」→ 自分の収入や支出の流れを整理でき、安心感が生まれる
「発信が怖い」→「自信を持って発信できるようになる」
3️⃣ その中から、最も心が動く変化をメインコピーにする。
これを繰り返すだけで、発信の軸がブレなくなります。
「商品を売る」のではなく、「変化の物語を伝える」という軸ができます。
顧客の「未来の一コマ」を描けているか?
顧客視点とは、「お客様の人生の中に入り込む力」です。
つまり、お客様があなたの商品を通して、「どんな自分になれるか」を具体的にイメージできるようにすることです。
それができれば、価格競争に巻き込まれることもなくなります。
お客様は「スペック」ではなく、「未来の自分」を基準に選ぶようになるからです。
例えば
- 「このコンサルを受ければ売上が上がる」ではなく、 「ビジネスに自信を持てるようになる」
- 「このデスクは丈夫です」ではなく、 「仕事がはかどる理想のワークスペースを作れる」
どちらの方が購買意欲が湧きますか?
間違いなく後者ですよね。
顧客視点を欠いた発信が招く3つの失敗
1️⃣ 自己満足型発信
自分が言いたいことばかりを話してしまう。結果、相手の関心に届かずスルーされる。
2️⃣ スペック型セールス
「何ができるか」ばかり説明してしまう。でもお客様は「その後の自分」にしか興味がない。
3️⃣ 抽象的すぎるメッセージ
「サポートします」「応援します」といった言葉では、変化が見えない。
これらを避ける唯一の方法が、「顧客視点の設計」です。
顧客視点を支える3つの問い
ここで、あなたの商品を見直すための質問を紹介します。
- この商品を買うことで、お客様の「何が変わる」?
- その変化は、どんな「感情」を生む?
- その感情を生む「きっかけの瞬間」はどこにある?
例えば、英会話教室であれば、「英語が話せるようになる」ではなく、「外国人と笑顔で会話できた瞬間」に価値がある。
このように、「感情の瞬間」にフォーカスするだけで、あなたのマーケティングは一気に変わります。
顧客視点を育てるやり方
1️⃣ レビュー分析
Amazonや楽天のレビュー、SNSコメントなどを100件は読み込みましょう。
そこにお客様の「言葉」があります。
「悩みのリアル」を理解する最強の教材です。
2️⃣ 顧客インタビュー
お客様に「なぜあなたを選んだのか?」を聞いてみてください。
その答えこそがUSP(独自の強み)を発見するヒントなります。
3️⃣ 共感ワードのメモ化
「その言葉、私もそう思ってた!」と反応があったフレーズをメモします。
それが、顧客の心に響くキーワードです。
まとめ(セクション3)
- 売れる人は、「顧客の未来」を描ける人。
- 顧客視点とは、「お客様の感情を先に設計する力」。
- 「この商品がどれほどすごいか」ではなく、「これを通じてあなたがどう変わるか」を伝えてみてください。
【セクション4】「伝え方」で9割決まる。価値を正しく届ける設計
このセクション4では、あなたがどれだけ素晴らしい商品を持っていても伝え方を間違えれば、売上は伸びませんという話をします。
実は、「売れるかどうかの9割」は「伝え方」で決まると言っても過言ではありません。
そしてその伝え方には、明確な法則があります。
「情報」を伝えても、人は動かない
多くの人がやりがちなミスがあります。
それは「正しい情報を伝えれば、理解してもらえる」と思っていることです。
でも、人は「理解」ではなく「感情」で動きます。
だから、情報だけを発信しても行動にはつながらない。
心理学的にも、人は「数字」より「ストーリー」に反応する生き物だとわかっています。
これをストーリーテリング効果といいます。
ストーリーテリング効果とは?
人は、単なるデータやスペックではなく、体験の物語に感情移入します。
例えば、次の2つのコピーを比べてみてください。
A→「この水は99.9%の不純物を除去します」
B→「子どもに「おいしい!」って言われた瞬間の、あの笑顔のために」
どちらが心に残りますか?
ほとんどの人がBと答えると思います。
人は理屈ではなく、「情景」に心を動かされる生き物です。
これが、伝え方の本質なんです。
「ベネフィットファースト」の鉄則
多くの人が、商品の説明を「機能」から話してしまいます。
でも正しい順序は、「機能」ではなく「変化」から話すこと。
例えば
❌「この講座ではマーケティングを学べます」
✅「この講座で集客の不安から解放されます」
言っている内容は同じなのに、受け手の印象はまるで違いますよね。
この順序の違いが、売れるかどうかの分かれ道と言えます。
「感情の設計」ができるかどうか
行動経済学者のダン・アリエリーはこう言っています。
「人は論理的な理由で行動するより、感情的な安心で行動する。」
つまり、人が購入を決める理由は「納得」ではなく「安心」
「この人なら信頼できそう」
「自分の気持ちを分かってくれそう」
この感情が購買スイッチを押します。
だからこそ、伝えるべきは「正しさ」ではなく「安心感」なのです。
安心感を生む3つの要素
1️⃣ 共感の言葉
「あなたもこんな経験ありませんか?」
相手が「自分のことを理解してくれている」と感じた瞬間、信頼が生まれます。
占い師の方で自分の性格や行動を言い当てると、信じてしまう現象。心理学ではコールドリーディングとも言われているテクニックです。
2️⃣ ビジョンの提示
「この方法で、あなたの理想の未来を実現できます」
人は「未来の自分」を見せられると動き出す生き物です。
3️⃣ 誠実なトーン
過剰な煽りや誇張表現は逆効果。
誠実なトーンが、ブランドの信頼性を支えます。
言葉の構造を整える「P.A.Sフォーミュラ」
伝わるメッセージには構造があります。
その代表的なフレームが「P.A.Sフォーミュラ」です。
- P(Problem)問題提起:「あなたは◯◯で悩んでいませんか?」
- A(Agitation)共感・問題の強調:「実はそれ、多くの人が同じことで悩んでいます。」
- S(Solution)解決策提示:「この商品なら、その悩みを解決できます。」
この3ステップを意識するだけで、どんな発信でも「心に届く構造」になります。
「伝える」と「説明する」は違う
ここで大事なのは、「伝える」と「説明する」を混同しないことです。
- 「説明」は、情報を正確に届けること。
- 「伝える」は、感情を動かすこと。
この違いを意識するだけで、あなたの発信の質は一気に変わるはずです。
例えば、「この机は高さ調節ができます」と言うのではなく、
「在宅ワークでも腰を痛めずに快適に働けるようになります」と伝える。
後者のほうが、「自分ごと」として想像できますよね。
言葉の強さを高める3つのテクニック
1️⃣ 数字と情景の組み合わせ
「3日で売上が30%伸びた」よりも、
「3日後、朝の売上レポートを見て思わず声が出た」の方が記憶に残ります。
2️⃣ 感情の語彙を使う
「嬉しい」「悔しい」「ほっとする」こうした感情語を使うと臨場感が増します。
3️⃣ 対比構造を使う
「変わる前」と「変わった後」を並べることで、変化を強調できます。
例:「寝不足で悩んでいた私が、今では朝5時に自然と目が覚めるように」
このようなテクニックを使うことで、言葉の強さを高めることができます。
まとめ(セクション4)
- 人は「情報」ではなく、「物語」で動く。
- 売れる言葉とは、「未来の情景」と「安心感」を同時に届けるもの。
- 伝える順番を変えるだけで、結果は180度変わる。
【セクション5】USP(独自の強み)を見つけて伝える方法
ここまで、「伝え方」の重要性をお話ししてきました。
でも、どれだけ上手に伝えても「他とどう違うのか」が分からなければ、選ばれません。
つまり次の課題は、あなたが選ばれる理由=USP(Unique Selling Proposition)を作ることです。
USPについては別途USPだけを解説した動画があるので、概要欄に貼っておきます。
ここでは、USPの重要ポイントについて解説していきます。
USPとは「たったひとつの選ばれる理由」
まずUSPとは、「なぜあなたの商品・サービスを選ぶべきなのか?」という、
お客様にとっての「たったひとつの明確な理由」のことです。
よく「うちは価格が安い」「納期が早い」といった違いを挙げる人がいますが、それは本当のUSPではありません。
なぜなら、それは「他社もすぐ真似できる差別化」だからです。
本当のUSPとは、あなたの想い・哲学・価値観・プロセスに宿るものなんです。
「機能の違い」ではなく「世界観の違い」
たとえば、ある整体院を例に考えてみましょう。
❌ 「国家資格あり・最新機器導入」
✅ 「痛みのない未来を一緒に作る整体」
後者の方が、圧倒的に印象に残りますよね。
なぜか?それは、「技術」ではなく「信念」を語っているからです。
お客様は、技術ではなく「自分の未来を理解してくれる人」に惹かれます。
これがUSPの本質です。
USPを見つける3つのステップ
ここからは、USPを発見するための具体的なステップを紹介します。
ステップ① お客様の「成功体験」を振り返る
これまであなたの商品を購入してくれたお客様の中で、特にうまくいった人・喜んでくれた人を思い出してください。
そして、こう尋ねてみましょう。
「なぜ私(またはこの商品)を選んでくれたんですか?」
多くの人は、「○○が分かりやすかった」「話し方が安心できた」など、
意外な視点を教えてくれます。
その一言の中に、あなたのUSPの「種」が隠れています。
ステップ② 他者との違いを3つ書き出す
競合と比べたときに、「これはうちだけの特徴だ」と思える点を3つ挙げてください。
例えば、
- 対応のスピード
- 提案の深さ
- フォローの丁寧さ
- 人柄や哲学
ここで大事なのは、「他社にない機能」ではなく、「他社にない姿勢」に注目することです。
「お客様の困りごとを自発的に先回りして解決しようとする積極的な姿勢」や「社員の挑戦を尊重し応援する文化」なども他社にない姿勢の一例です。
このように他社との差別化ポイントを「姿勢」に注目して整理すると、独自性が伝わりやすくなります。
ステップ③ 「自分だからできる価値」を一言にまとめる
最後に、「あなたにしかできない価値」を一言にまとめてみましょう。
例えば
- 「相手の強みを見つけて言語化するのが得意」
- 「数字よりも人の感情を読み取るのが得意」
- 「売り込みが苦手な人でも成果を出せる仕組みを作る」
この一言が言語化できた瞬間、あなたのUSPは完成です。
そして、その一貫した軸がブランディングを作っていきます。
「差別化」ではなく「共感化」
USPを考えるとき、多くの人が「差別化」にフォーカスします。
しかし、今の時代に必要なのは「共感化」です。
人は「違うもの」よりも、「自分に合うもの」を選びます。
つまり、「この人の考え方が好き」「この人の価値観に共感する」そう感じてもらえることこそが、選ばれる理由になります。
ブランドは、共感の積み重ねで作られます。
よくある業界事例
マーケティング支援をしていると、
「USPがない」と悩む方の多くが、実は自分の中にUSPを持っているのに気づいていません。
例えば、あるカフェオーナーさん
当初は「豆の種類」「焙煎方法」で他店との差別化を図ろうとしていました。
ところが、お客様にアンケートを取ってみると、
返ってきた答えはこうでした。
「ここに来ると、なんだか安心できる。」
「店主の笑顔が好きなんです。」
そう、USPは「技術」ではなく「体験」だったのです。
その後、カフェのコンセプトを「心を整える場所」に変えたところ、常連客が増え、口コミが自然と広がっていきました。
USPは戦略ではなく信念から生まれる
USPは、マーケティングのテクニックではありません。
「あなたは何のために、その商品・サービスを提供しているのか?」
この問いに対する信念の言葉が、最も強いUSPになります。
人は商品を買うのではなく、想いに共感して動く。
あなたの中にある「なぜ」を言語化できたとき、その想いが伝わり、価格以上の価値を感じてもらえるようになります。
まとめ(セクション5)
- USPとは「他と違うこと」ではなく、「あなたにしかできない価値」。
- 技術ではなく、想い・姿勢・体験にこそ強みがある。
- 共感で選ばれるブランドは、信念から作られる。
【セクション6】「比較」ではなく「選ばれる理由」を作るマーケティング
ここまでで、USP(独自の強み)の作り方をお話ししました。
このセクションでは、そのUSPをどう活かして「価格競争に巻き込まれない構造」を作るかを解説していきます。
「比較される構造」にいる限り、価格で負ける
まず、覚えておいてほしいことがあります。
それは、比較されているうちは、まだ伝わっていないということです。
お客様は違いがわからないと、「安い方」で選びます。
これを心理学でいうヒューリスティック思考。
人は複雑な判断を避け、もっとも分かりやすい基準(価格や数字)で選択をする傾向があるとお伝えしました。
つまり、「どこで買っても同じ」と見なされている状態では、あなたがどれだけ努力しても、「価格」が判断基準になってしまいます。
だからこそ、比較されない構造を設計することが必要なんです。
比較から抜け出す3つの方法
ここからは、私がこれまでマーケティング支援を通して見てきた中でも
「選ばれるブランド」が共通して実践していた3つの方法を紹介します。
方法① 「ストーリー」で差別化する
商品を説明する前に、「なぜそれを作ったのか」を伝えましょう。
人は「理由」に共感します。
例えば、同じ英会話スクールでも
❌「ネイティブ講師が指導します」
✅「海外で「話せず悔しい思いをした自分」を救いたくて、このスクールを作りました!」
この「理由の物語」があるだけで、教える内容が同じだったとしても全く違う印象になります。
共感は「機能」ではなく、「背景」から生まれるのです。
ストーリーを語ることは、自分のビジネスに「人間味」を与えてくれます。
あなたの想いが伝わった瞬間に、お客様は「商品」ではなく「あなた」を選び始めます。
方法② 「プロセス」で差別化する
次に大切なのが、「どんな過程で結果を生み出すのか」を伝えることです。
多くの人は結果ばかりを訴求します。
「最短で売上アップ」「たった3日で成果」
でも、今の消費者は非常に賢いです。
結果よりも、「その結果に至る道筋」に信頼を感じます。
例えば、
「最短1週間で結果が出ます」よりも、
「毎日10分の習慣で確実に結果を積み上げていきます」
の方が、現実味があって信頼される。
人は「努力のリアリティ」を感じた瞬間に安心します。
方法③ 「理念」で差別化する
そして、3つ目がもっとも本質的。
それが理念で差別化するということです。
理念とは、「あなたが何を信じてこの仕事をしているのか」
これを言葉にできるかどうかで、ブランドの深さが決まります。
「理念」が生む信頼の構造
理念を掲げると、お客様との関係性が変わります。
「発注者」と「受注者」という上下関係ではなく、
「共に目指す仲間」という信頼の関係になるんです。
心理的にも、理念に共感した顧客は価格に対して寛容になります。
彼らは「コスト」ではなく、「価値」を見て判断するようになるからです。
これは私もマーケティング支援をさせて頂いてる中で凄く意識しています。
ドライブで例えると
社長が運転席に座り、私が助手席に座って共に、同じ目的地に向かっている。
基本的には、目的地は売上UPなのですが、お互いにその目標に向かって車を走らせる仲間だという意識を持ってやっています。
なので、時に言いたくないことを言う時もあります。
でも、それはお互いが本気でその目的地に行きたいと願っているからであり、そのような関係で私はマーケティング支援をしたいと考えています。
少しでも共感できる方は、概要欄のお問い合わせからご連絡ください。
少し、話が脱線しましたが、比較されないブランドの3条件を見ていきましょう。
比較されないブランドの3条件
1️⃣ 独自のストーリーを語っている
「どうしてこの仕事をしているのか」が明確。
2️⃣ 一貫した世界観がある
SNS・動画・デザイン・言葉、すべてが同じ方向を向いている。
3️⃣ 短期利益より長期信頼を優先している
「すぐ売る」ではなく、「信頼を積み上げ」姿勢。
この3つが揃うと、あなたのブランドは自然と「比較リストの外側」に出ます。
そして、価格競争とは無縁のポジションに立てるようになります。
価格競争を抜け出すマインドセット
ここで少しマインドの話をします。
多くの人は「高くしたら売れなくなるのでは…」と不安になります。
でも実は、価格を上げることこそが「信頼の証」なんです。
価格には「覚悟」が現れます。
あなたの覚悟が見えるほど、人は安心してお金を払います。
価格を安くすることは「逃げ」ではなく、「信頼を下げるリスク」になることもあります。
だから、価値を高める努力をして、その価値を正しく伝える。
これが、真のマーケティングです。
あなたの理念を言語化する3つの質問
1️⃣ なぜこの仕事をしているのか?
(あなたが心から解決したい問題は?)
2️⃣ 誰を幸せにしたいのか?
(あなたが最も救いたい相手は誰?)
3️⃣ どんな世界を作りたいのか?
(あなたの商品を通じて実現したい理想は?)
この3つの答えをつなげると、理念が言葉になります。
その言葉こそが、あなたを「比較されない存在」にする武器となります。
まとめ(セクション6)
- 比較されるうちは、「違い」が伝わっていない。
- 差別化ではなく、理念と信念で選ばれるブランドを作ろう。
- ストーリー・プロセス・理念、この3つを発信軸に据えることが、価格競争を超える唯一の方法。
【セクション7】お客様の購買心理を設計する「マーケティングの階段」
ここまでで、「伝え方」や「USP」、そして「理念」を整える重要性をお話ししてきました。
ここからは、それらを「仕組み化」していく段階に入ります。
つまり、「どうすればお客様が自然に商品を欲しくなる流れを作れるのか?」
このセクションでは、その「心理の階段」を設計していきます。
売れる人は「偶然」ではなく「設計」で売っている
多くの人は「売れた理由」を感覚で語ります。
「たまたまバズった」「紹介が来た」「運が良かった」などなど。
確かに、運の要素もあることは否定しません。
でも、ビジネスで安定的に成果を出している人は、偶然ではなく設計で売っています。
つまり、「お客様の心理の流れ」を理解し、それに合わせて発信・導線・オファーを整えている。
その構造を私はよく「マーケティングの階段やファネル設計」と呼んでいます。
「知ってもらう」だけでは売れない理由
多くの人が勘違いしているのが、「認知されれば売れる」という考え方。
でも実際には、「知ってもらっただけ」では人は動きません。
人が購買に至るまでには、心理的な段階があります。
これは「購買ファネル」や「AIDMAモデル」としても知られています。
Attention(注目)
→ Interest(興味)
→ Desire(欲求)
→ Memory(記憶)
→ Action(行動)
これが基本構造。
ただ、現代のSNS時代にはもう一段階追加されています。
それが、Share(共有)
つまり、「買って終わり」ではなく「買って広める」
この「共有」こそが次の顧客を生む、現代マーケティングの最大の特徴です。
SNS時代の購買心理モデル「AISAS」
今の時代に合う心理設計を表すモデルが「AISAS(アイサス)」です。
- Attention(注目):まずあなたの存在を知る。
- Interest(興味):もう少し知りたいと思う。
- Search(検索):調べてみる。
- Action(行動):購入や登録をする。
- Share(共有):良かった体験を人に伝える。
ここで重要なのは、SNSの発達によって「Search」と「Share」の力が極端に大きくなっているという点です。
つまり、「買う前の検索」と「買った後の共有」を意識して設計できる人が、売り込まずに売れる人なんです。
なぜなら、お客様が勝手にあなたの商品やサービスを無料で広めてくれるからです。
まさに、お客さんがお客さんを呼ぶという好循環に入ります。
階段設計の考え方→「導線」と「感情」を一致させる
お客様の心理には段階があります。
それを理解せずに「すぐ購入してください」と言っても、信頼の積み上げがないため動きません。
恋愛で例えるなら、道を歩いている人にいきなり結婚してください!と言っているようなものです。
理想的な流れは、次のようになります。
1️⃣ 投稿や広告で「認知」してもらう
→ あなたの世界観や価値観に触れてもらうことが目的。
2️⃣ ストーリー投稿やライブ配信などで「共感」を得る
→ 「この人、自分のこと分かってくれてる」と感じてもらう。
3️⃣ 無料コンテンツやLINE登録などで「信頼」を積み上げる
→ ここで教育が始まります。(厳密にはYouTubeなど長尺の動画であれば、認知+教育ができる)
4️⃣ 個別相談・セミナー・説明会などで「納得」を作る
→ 「なるほど、だから必要なんだ」と腹落ちさせる。
5️⃣ 商品購入で「行動」に移す
→ 無理なセールスではなく、自然に欲しくなる。
6️⃣ 体験後のフォローで「リピート・紹介」に繋げる。
これが「売り込まずに売れる」構造です。
まさに心理の階段を一段ずつ上がってもらうイメージです。
教育系スクールの導線改善
あるオンラインスクールでは、当初「LP(ランディングページ)から直接申込み」だけの導線でした。
一見スムーズに見えますが、実際にはコンバージョン率が低かったです。
なぜなら、「納得する前に買う」設計になっていたからです。
そこで導線を再構築しました。
- 1日目:創業者の想い(なぜこのスクールを作ったのか)
- 2日目:受講生の変化ストーリー
- 3日目:学びの中身を紹介
- 4日目:無料体験の案内
- 5日目:受講の流れと特典案内
このようにステップメール形式で「理解と納得」を順に作っていったところ、成約率が 2.3倍 にアップしました。
人は、「納得してから」行動します。
マーケティングとは、「売上の流れを作ること」とも言えますが、「納得の流れを設計すること」でもあります。
感情の連鎖をデザインする
購買行動の背景には、感情の流れがあります。
「気になる」→「信頼する」→「欲しくなる」→「行動する」→「感動する」
この流れを意図的にデザインすることがマーケティングの核心です。
逆に言えば、この流れを無視して「売り込み」だけすると、
信頼を失い、短期的にしか売れません。
「知る→信頼→購入→共有」を設計する実践ヒント
1️⃣ 知ってもらう:広告・SNSで世界観を伝える
→ 「あなたは何者か?」を発信する段階。
2️⃣ 信頼してもらう:教育コンテンツで価値提供
→ 無料で「助けられた」と感じた人は、有料でも信頼します。
3️⃣ 購入してもらう:納得導線を丁寧に設計
→ 売る瞬間ではなく、「買いたくなる流れ」を作る。
4️⃣ 共有してもらう:感動体験を届ける
→ 購入後のフォロー体験が、次の集客装置になります。
「購買心理の階段」を整えるチェックリスト
- [ ] 商品を知る前の人に、何を見せるか?
- [ ] 興味を持った人に、どんな「次の一歩」を提案するか?
- [ ] 信頼を深めるために、どんな情報を提供するか?
- [ ] 購入の決断を後押しする「安心材料」はあるか?
- [ ] 購入後に「感動」を作る仕掛けはあるか?
これらが一つずつ設計されている人は、
もはや「営業」をしなくても商品が売れていきます。
まとめ(セクション7)
- 売上は「偶然」ではなく「心理設計」から生まれる。
- お客様の感情の流れに沿って「導線」を整えることが本質。
- 知ってもらう → 信頼される → 納得してもらう → 感動してもらう この階段を作れれば、売り込まずに売れる。
【セクション8】信頼が積み上がる「コンテンツ戦略」とは?
ここまでで、「お客様の心理の階段」を設計する重要性をお伝えしました。
では次に、どうやって「信頼」を積み上げるのか?
その仕組みを具体的にお話ししていきます。
信頼は「一度の投稿」では生まれない
多くの人は、発信を「露出を増やすため」と考えています。
でも、本当の目的は「露出」ではなく「信頼構築」です。
SNSもYouTubeもブログも、すべては「信頼の積立口座」
投稿するたびに、少しずつ信用残高が貯まっていく。
そして、ある日「この人なら間違いない」と思ってもらえる。
その時、セールスをしなくても今までの信頼残高を放出すれば、自然に売れていく
それが「信頼ベースのマーケティング」です。
心理学で見る「単純接触効果」
信頼を積み上げるうえで、心理学的に重要なのが「単純接触効果(ザイアンス効果)」です。
人は、何度も見聞きした相手に自然と好感を抱く。
つまり、継続的な発信=信頼の積み重ねです。
例えば、最初の投稿ではスルーされても、
3回、5回、10回と触れた瞬間に「なんか気になる人だな」と印象が変わります。
発信とは、「信頼の時間投資」なんです。
私のところに面談に来る方に、どの動画と何本くらい動画見ましたか?と聞くと平均2、3本見て問い合わせをくれます。
つまり、2、3本でもしっかりと価値提供できれば問い合わせは来ると言うことです。
「露出」ではなく「教育(価値提供)」の発信へ
信頼を積み上げたいなら、発信の目的を「売ること」から「教育すること(価値提供)」へ切り替えましょう。
教育とは、お客様の理解を深めること。
あなたの商品やサービスの価値を、相手が「自分ごと」として理解できるように導くことです。
例えば、私のような広告代理店なら
「リスティング広告の運用代行をしています」ではなく、
「なぜクリック率だけを追うと売上が落ちるのか?」と解説する発信をする。
このように、「知識で信頼を生む」コンテンツが教育型(価値提供型)の発信です。
信頼を積み上げる3種類のコンテンツ
あなたの発信を、次の3種類に分けて考えると戦略が整理しやすくなります
1️⃣ 信頼構築型コンテンツ(あなたの想い・哲学・ストーリー)
例:「なぜこの仕事をしているのか」「過去にどんな失敗をして今に至るのか」
→ 「人間味」を伝えることで、共感を得られます。
2️⃣ 教育型コンテンツ(ノウハウ・ハウツー・専門知識)
例:「広告の成果を上げる3つの視点」「顧客単価を上げる心理設計」
→ 「専門性」を伝えて、信頼を強化します。
私のyoutubeはこの2番のハウツー型を取り入れています。ただし、このハウツーだけだとコアなファンはつきません。コアなファンをつけるには情緒やもっと人間味を出さないといけません。ここら辺が私の課題かなと感じています。
3️⃣ 共感型コンテンツ(感情的な支え・寄り添い)
例:「結果が出なくて焦っている人へ」「完璧を求めすぎなくて大丈夫」
→ 「安心感」を与えることで、長期フォロワーが増えます。
この3つのコンテンツをバランス良く発信することで、
「共感 → 信頼 → 尊敬 → 行動」という自然な流れが生まれます。
「誰のために、何を伝えるか」を固定する
コンテンツ戦略を設計するとき、最も重要なのが
「誰に向けて発信しているか」を固定すること。
フォロワーを増やすことより、フォロワー1人の理解度を深めることを意識する。
「この発信は、過去の自分のように悩んでいる人へ」
「この動画は、今まさに壁にぶつかっている起業家へ」
このように相手を具体的に描くほど、発信の温度が上がり、信頼が加速します。
「発信は信頼の積立」3原則
1️⃣ 継続は「量」ではなく「一貫性」
毎日投稿よりも、「世界観を崩さずに発信を続ける」ことの方が大切です。
2️⃣ 短期的な反応より「記憶」を残す
バズを狙う発信ではなく、半年後に「あの人の言葉が残ってる」と思われる発信を。
3️⃣ 信頼残高は「誠実さ」で貯まる
少しの炎上、強引な売り込み、一度の裏切りが、数ヶ月の信頼を一瞬で消します。
誠実な発信姿勢は、最大の資産となります。
わざと炎上して本当にコアなファンだけを残す方法もありますが、ここでは割愛します。
「教育型発信」を育てる具体ステップ
1️⃣ Q&Aリストを作る
お客様やフォロワーさんからよく受ける質問を20個書き出します。
その答えを投稿や動画で解説するだけで、価値提供コンテンツが量産できます。
2️⃣ Before→After構成を意識する
変化の物語を伝えることで、感情的な説得力が増します。
3️⃣ 声を可視化する
お客様のコメント・メッセージを拾って発信に反映。
リアルな声ほど、新しい読者の心を動かします。
「信頼の構造」はコンテンツの深さで決まる
コンテンツの信頼度は、「量」ではなく「深さ」で決まります。
1本の投稿でも、心の奥に届く内容なら、たった1人の人生を変えることができます。
逆に、100本投稿しても「薄い内容」では印象に残りません。
だからこそ、「発信すること」より「何を伝えるか」を丁寧に磨く必要があります。
まとめ(セクション8)
- 発信は「露出」ではなく「信頼の積立口座」。
- 信頼は教育・共感・誠実さの3要素で積み上がる。
- コンテンツとは、「売るため」ではなく「理解してもらうため」にある。
- 信頼が積み上がるほど、あなたは「売り込まなくても売れる人」になる。
【セクション9】リピートと紹介を生む「体験設計マーケティング」
ここまでのセクションでは、「どうやって信頼を積み上げて、購買に繋げるか」という前半戦をお話ししてきました。
しかし、真に強いビジネスとは、「買ってもらった後」から始まります。
お客様が「またお願いしたい」「誰かに紹介したい」と思う
その状態を作るのが体験設計マーケティングです。
売上の8割は「既存顧客」から生まれる
マーケティングの世界には、こんな有名な法則があります。
「新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍。」
これは「1:5の法則」と呼ばれるもので、リピート顧客こそがビジネスの土台だということを示しています。
実際、どんな業界でも「安定している企業」はリピート率が高い。
そして、その理由の多くは「購入体験」にあります。
「購入体験」は、商品そのものより記憶に残る
心理学では「ピーク・エンドの法則」と言われます。
人は、体験全体を平均で覚えるのではなく、
一番印象的だった瞬間(ピーク)と、最後の瞬間(エンド)で記憶するのです。
ピークエンドの法則とも呼ばれています。
例えば、レストランで料理が少し遅れても、最後にシェフが丁寧に挨拶してくれたら「いいお店だった」と感じます。
逆に、どんなに味が良くても最後の対応が悪ければ「もう行かない」となる。
つまり、「最後の体験」が印象を決める。
ここにこそ、リピートと紹介を生む秘密があるんです。
よく居酒屋さんで会計が終わったら、無料で入浴剤をくれるお店がありますが、あれはピークエンドの法則を意識したものだと思います。
単純に入浴剤をたくさん貰ったから配っているだけの可能性もありますが、どちらにしろ最後に何かお客様を感動させられることをすると強烈に記憶に残ります。
私の持っている海外向けのECでは、商品とは別にサプライズでダンボールに大量の日本のお菓子と日本の風景が絵がれているポストカードをプレゼントしています。
ECにおいては商品が到着して箱を開けるその瞬間がピークだからです。
そのピークにサプライズで日本のお菓子が大量に入っていたら、絶対嬉しいですよね。
このようにお客様の気持ちを考えて狙った施策を打ちます。
私のマーケティングサポートではこの辺の戦略からファネル設計まで一気通貫でサポートしています。
リピートを生む体験設計の3ステップ
体験を設計する際には、次の3つのステップを意識しましょう。
ステップ① 購入前の「期待」をデザインする
「買ったらどうなるのか?」という期待を、リアルにイメージしてもらう。
購入前の段階で、「期待の物語」を描けるかどうかが重要です。
例:「この講座を受けた後、あなたの集客は自動化のフェーズに入ります」
→ 結果ではなく、「未来の姿」を想像させる言葉が効果的です。
ステップ② 購入直後の「安心」を提供する
実は、お客様が最も不安を感じるのは「購入直後」です。
「本当にこれで良かったのかな?」という後悔の感情=バイヤーズリモース(買い手の後悔)が起こる瞬間があります。
このタイミングでフォローがあるかどうかが、リピート率を大きく左右します。
例えば、
- 「あなたの選択は間違っていません。これからの変化を一緒に作っていきましょう」
- 「最初の3日間はこれだけやってみてください。変化が出やすいですよ」
こうした「購入後メッセージ」は、小さな安心を与える大きな仕掛けになります。
ステップ③ 体験後の「感動」を設計する
そして最後に、「感動」を作る。
感動とは、想定を超える体験のこと。
つまり、「想像していたよりも良かった」と思ってもらうことです。
これは高価な特典や豪華な演出でなくても大丈夫です。
例えば、
- サービス終了後に「あなたの成長記録」をまとめてプレゼントする
- 担当者から直筆のメッセージを添える
- 感謝を込めた一言動画を送る
- 居酒屋であれば、その場で写真を撮って、すぐ印刷して会計時に無料で渡す
このような「人の温度を感じる体験」こそが、記憶に残ります。
この相手の期待値を超える努力は私も常に意識しています。
この動画1本とっても、ユーザーが時間を割いて動画を見ようとしてくれているので、その方の期待を裏切らないような内容にしたいと考えています。
また、私のチャンネルを登録してくれている人は、今後の私の動画に対して期待を込めてチャンネル登録してくれていると思うので、可能な限りその期待に応えることがコンテンツ製作者の義務だと私は考えています。
「感動の瞬間」が紹介を生む
加えて人は、「感動」したときに他人に話したくなります。
心理学ではこれを「自己拡張理論」と呼びます。
感動体験を共有することで、自分の価値を高めたいという心理が働きます。
つまり、紹介は仕組みではなく感情から生まれる。
だから、紹介を増やしたいなら「紹介キャンペーン」よりも「感動設計」を優先しましょう。
そして紹介キャンペーンをやるのであれば、必ず双方に(紹介する方もされる方も)同じくらいのメリットがあるようにしてください。詳しい説明はここでは割愛します。
「買って終わり」ではなく「関係が始まる」
マーケティングの本質は、「関係性の設計」でもあります。
商品を売った瞬間に終わるのではなく、「ここからお客様とのストーリーが始まる」という意識を持つ。
この意識をチーム全体で共有できている企業ほど、顧客満足度と紹介率が高い。
数字を追うマーケティングから、「信頼を積み上げるマーケティング」へ。
ここが、ビジネスのステージが変わる分岐点と考えています。
まとめ(セクション9)
- リピートと紹介は、「感動体験」から自然に生まれる。
- ピーク・エンドの法則を意識し、「最後の印象」を最高にする。
- 紹介は仕組みではなく、感情の共鳴から起きる。
- 「買って終わり」ではなく、「そこから始まる関係性」をデザインしよう。
【セクション10】マーケティングを「仕組み化」して自動で信頼が積み上がる状態へ
これまでお話ししてきた内容をまとめると
マーケティングの本質は、「売り込む」ことではなく「信頼を積み上げる」こと。
そして、最終的に目指すべきは、「信頼が自動で育つ仕組み」を作ることです。
「仕組み化」とは手を抜くことではない
多くの人が誤解しているのが、「自動化」や「仕組み化」という言葉の意味です。
これは「自分が楽をする仕組み」ではありません。
正しくは、「お客様との信頼を、安定して育て続ける仕組み」です。
例えば、営業メール・動画・教育コンテンツ・フォロー体験。
これらを一度作っておけば、あなたが寝ている間にもお客様に価値が届く。
つまり、「あなたが話さなくても、信頼が積み上がる状態」
これこそが、仕組み化の本当の目的です。
「信頼の自動化」を構成する3つの要素
仕組み化の構造はシンプルです。
すべての成功企業は、次の3つを組み合わせています
1️⃣ 自動で届ける仕組み(オートメーション)
2️⃣ 自動で教育する仕組み(ナーチャリング)
3️⃣ 自動で繋がり続ける仕組み(リテンション)
それぞれ、詳しく解説していきます。
① 自動で届ける仕組み(オートメーション)
まずは、「価値ある情報を定期的に届ける仕組み」を作ることです。
メール・LINE・SNS・YouTubeなど、媒体は何でも構いません。
例えば、週に1回でも良いので「○曜日の○時に価値提供を自動配信」する。
そのリズムを決めるだけで、あなたの存在はお客様の「日常の一部」になります。
この「習慣的接触」が、長期的な信頼を育てます。
単発の広告よりも、「毎週届くメッセージ」の方が圧倒的に記憶に残ります。
② 自動で教育する仕組み(ナーチャリング)
次に重要なのが、教育の自動化です。
これは「見込み客があなたの商品を理解し、欲しくなるまでの流れ」を
あらかじめ設計しておくことを意味します。
例えば、次のようなステップ配信を考えてみてください
- 【Day 1】あなたの理念・想い(なぜこの商品を作ったのか)
- 【Day 2】顧客の変化ストーリー(共感を生む実例)
- 【Day 3】よくある失敗例(問題意識を深める)
- 【Day 4】商品が生まれた背景(信頼を高める)
- 【Day 5】自然なオファー(売り込まない提案)
このように、「教育の流れ」を自動で届けることで、「営業されている感覚なく信頼が積み上がります。
しかも、毎回同じ品質で届けられる。
人間の感情に左右されない安定した体験を提供できるのが、この仕組みの強みです。
③ 自動で繋がり続ける仕組み(リテンション)
そして3つ目。
これは、「購入後のお客様と関係を継続させる仕組み」です。
購入がゴールではなく、「信頼関係の始まり」と捉える。
だから、購入後こそフォローが重要なんです。
例えば、
- 商品購入後の自動メールで「使い方ガイド」や「よくある質問」を送る。
- 数日後に「フォロー動画」や「小さな成功事例」を紹介する。
- 1ヶ月後に「成果チェックシート」や「体験インタビュー」を案内する。
このように「買って終わり」ではなく「買ってからも寄り添う設計」を自動化する。
それだけでリピート率・紹介率が格段に上がります。
実例:教育コンテンツの自動化で売上を倍増させた講師
あるコーチング講師の事例を紹介します。
この方は、最初の頃は毎回Zoomで1対1の説明をしていました。
熱意は伝わるけれど、時間がかかりすぎて拡大できなかった。
そこで、「信頼構築の流れ」を自動化しました。
1️⃣ 初回の「理念動画」を自動配信(想いの共有)
2️⃣ 成功事例を5本のメールで紹介(共感・信頼形成)
3️⃣ Q&A動画で不安を解消(心理的ハードルを下げる)
4️⃣ 自動で「相談フォーム」へ誘導(自然なアクション設計)
この仕組みによって、月50件だった申し込みが、同じ労力で120件に増加。
本人が喋らずとも、動画と文章が代わりに「信頼を積み上げてくれる」状態を作れたのです。
「人の温度感」と「仕組み」のバランスが鍵
自動化というと、冷たい印象を持つ人も多いでしょう。
でも、重要なのは「温かい仕組み」を作ることです。
仕組みはあくまで「体験を届ける器」
そこに乗せるのは、あなたの想い・言葉・表情です。
動画でも文章でも、「あなたの声」で届けること。
これがあるだけで、どんな自動化も「人間味」を失わずに機能します。
仕組み化で自由を取り戻す
仕組みを作る最大のメリットは、「時間の自由」を取り戻せることです。
発信・営業・対応に追われる日々から抜け出し、「価値づくり」と「顧客体験」に集中できる。
あなたの代わりに信頼を積み上げる仕組みを持てば、ビジネスの「質」も「安定性」も劇的に上がります。
仕組み化を始める最初の3ステップ
1️⃣ 信頼を積み上げる「流れ」を可視化する
「出会い → 教育 → 購入 → フォロー → 紹介」
この流れを図解にして、どこを自動化できるかを考えます。
2️⃣ 1箇所だけ自動化してみる
いきなり全体を作ろうとせず、「教育メール1本」などから始める。
3️⃣ 効果を数値で確認し、改善する
開封率、再生率、クリック率、リピート率など、
「信頼の見える化」を行うことで、精度が上がります。
正直全てを仕組みかすることも可能です。
広告などでリストイン(出会い)→ LINEやメルマガのステップメール価値提供(教育)→ 教育終了後購入フォームを自動送信(必要であれば動画も用意)→ 購入後のフォローは講座形式にして過去の受講生からのQ&Aを動画化 → 最後に紹介数に応じて「ランク」「特典」「バッジ」を付与するロイヤリティープログラムを用意(紹介)これを全て構築するのはかなり大変ですが、全てを仕組み化することは可能です。
まとめ(セクション10)
- 仕組み化とは、「信頼を自動で育てる仕組み」を作ること。
- 教育・フォロー・発信を自動化すると、あなたの価値が「24時間稼働」する。
- 温度を失わずに自動化することが、次の時代のマーケティング。
- 仕組みがある人は、働かなくても「信頼が増え続ける人」になる。
【セクション11】マーケティングの本質は「売る」ではなく「育てる」
ここまで長い時間、お付き合いいただきありがとうございます。
この動画のテーマ「良い商品なのに売れない」を卒業するの最後にお伝えしたいのは、マーケティングの本質についてです。
「売る」マーケティングの限界
多くの人が、マーケティングを「売るための技術」と捉えています。
しかし実際は、それだけでは長続きしません。
「売ること」をゴールにしてしまうと、
お客様は「買う側」、あなたは「売る側」という対立構造になってしまいます。
この構造では、信頼は積み上がらない。
短期的な売上は作れても、長期的な関係は築けない。
だからこそ、次の時代に必要なのは「売る」ではなく「育てる」マーケティングです。
今やSNSなどの発達もあり、お客様と企業とのコミュニケーションが取りやすくなっています。
だから、売って終わりではなく、長期的な関係構築を目指す育てる意識が重要なのです。
「育てる」とは、信頼と理解を時間をかけて作ること
「育てる」とは、時間をかけて信頼と理解を作ることです。
商品を売るのではなく、「お客様の成長を支援する」という姿勢です。
例えば、教育業界を見てみましょう。
優れた教師は「知識を与える人」ではなく、「生徒の成長を導く人」です。
マーケティングもまったく同じ。
あなたが提供しているのは「商品」ではなく、
その商品を通してお客様が「より良く変わっていく体験」です。
この意識に切り替わった瞬間、発信も提案も変わります。
「売上」ではなく「信頼残高」をKPIにする
これからのマーケティングにおいて最も重要な指標は、「どれだけの信頼を積み上げたか」です。
お客様が「あなたの発信を見て役立った」と感じた数。
「この人なら間違いない」と思ってくれた瞬間。
「紹介したい」と感じてくれた温度。
それらが、すべて「信頼残高」なんです。
そして信頼残高は、売上よりもはるかに長く残ります。
一度信頼を築いたお客様は、何度も戻ってきます。
だからこそ、最も価値ある資産は「信頼」なんです。
「マーケティングは教育であり、共育でもある」
私はよく、マーケティングを「教育」に例えます。
でも最近では、こう感じています。
マーケティングとは、「共に育つこと」。
つまり、共育(ともいく)なんです。
お客様が成長すれば、あなたのビジネスも成長します。
お客様が成功すれば、その声が次のお客様を呼びます。
この「信頼の循環」が起きた瞬間、マーケティングは永続的な仕組みになります。
「信頼経済」の時代が来ている
今、私たちは「情報」よりも「信頼」に価値がある時代に生きています。
AIもテクノロジーも進化し、情報の差はどんどんなくなっていく。
だからこそ、最後に残るのは「誰から買うか!」
「この人から買いたい」「このブランドなら安心できる」その「人間的な信頼」こそ、最大の競争優位性です。
これからは、「信頼をどう設計するか」がマーケティングの核心になります。
「マーケティング=信頼のデザイン」
マーケティングとは、信頼をデザインすること。
あなたとお客様の間に、どんな感情を流すかを設計すること。
- 出会った瞬間に「この人、誠実そう」と思われるか。
- 話を聞いて「自分を理解してくれている」と感じてもらえるか。
- 商品を使って「想像以上だった」と感動してもらえるか。
これらすべてが、マーケティングの仕事です。
信頼を意図的にデザインできる人こそ、真のマーケターです。
これからの時代に必要な3つの姿勢
1️⃣ 誠実に伝える
誇張ではなく、事実と情熱で伝える。
2️⃣ 相手の成果を自分の成果とする
売上ではなく、顧客の成功をKPIにする。
3️⃣ 短期よりも長期を見据える
「今すぐの売上」よりも、「10年続く信頼」を育てる。
この3つの姿勢を持つだけで、あなたのマーケティングは「売る」から「育てる」へと変わります。
最後に「良い商品なのに売れない」を卒業するために
もし今あなたが、「良い商品なのに売れない」と感じているなら、
その原因は「商品」ではなく、「伝わり方」と「信頼構築の流れ」にあるかもしれません。
だから焦らず、時間を味方にしてほしいんです。
信頼は一瞬では生まれない。
けれど、コツコツと積み上げた信頼は、決して裏切らない。
そして、信頼を育てるマーケティングを実践すれば、
あなたのブランドは「売る努力」ではなく「選ばれる流れ」に乗ります。
まとめ
- マーケティングの本質は、「信頼を育てること」
- 売上よりも、信頼残高を増やすことに集中する。
- 顧客を「取引相手」ではなく「共に成長するパートナー」として見る。
- 仕組みではなく、想いの継続がブランドを作る。
- 「売る」から「育てる」へ、この意識転換が、すべてを変えます。
「良い商品なのに売れない」原因は「商品力」ではなく「伝え方」と「信頼構築の流れ」にあると解説しています。現代において「良い商品を作れば売れる」という考えは通用しません。
まず、人は合理的にではなく感情的に購買を決めます。顧客が求めているのは商品の機能ではなく、「その商品を手にしたお客様がどう変わるか」という「変化」や「未来の情景」です。売れるマーケティングの第一歩は、情報を詰め込みすぎず、伝えるべきメッセージを削り、お客様が得る変化に焦点を絞ることです。
価格競争を避けるためには、「安さ」ではなく「選ばれる理由」を作る必要があります。この独自の強み(USP)は、技術的な違いではなく、あなたの想い、信念、哲学といった「世界観の違い」に宿ります。他社との「差別化」よりも、顧客との「共感化」が重要です。
売上は「偶然」ではなく、顧客の心理の流れに沿ってデザインされた「仕組み」から生まれます。マーケティングの発信は「露出」のためではなく、顧客の理解を深める「教育」と「信頼の積立口座」として機能させるべきです。コンテンツを通じて信頼残高を積み上げ、購入後も「ピーク・エンドの法則」に基づいた感動体験(例:想定を超えるフォローやサプライズ)を設計することで、リピートや紹介が自然発生します。
最終的に、マーケティングの本質は「売る」技術ではなく、お客様の成長を支援し、信頼と理解を時間をかけて作っていく「育てる」(共育)という姿勢にあります。信頼残高を最重要KPIとし、誠実な発信と長期的な関係性をデザインすること、そしてそのプロセスを自動化する仕組みを構築することが、価格競争とは無縁のブランドを築く鍵です。
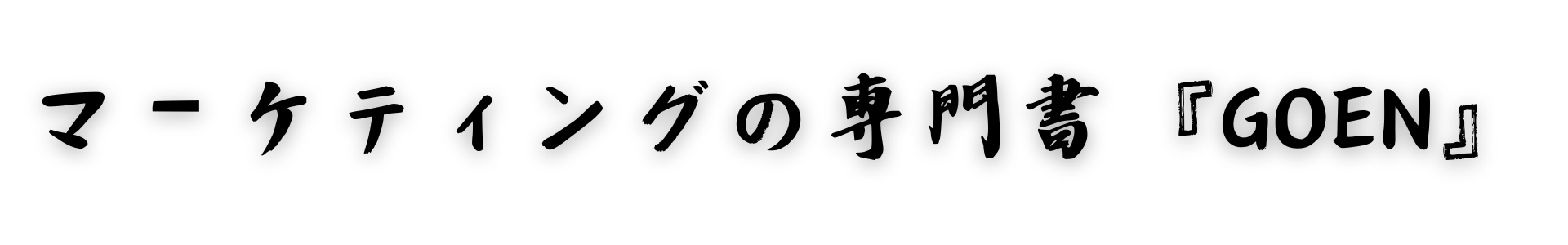

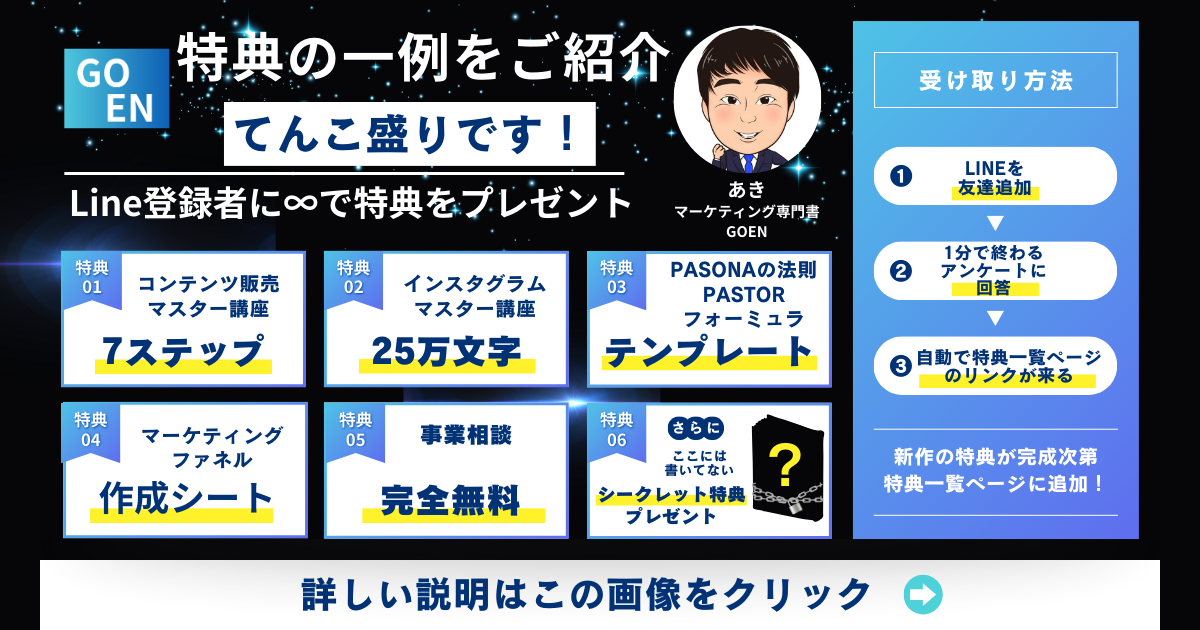




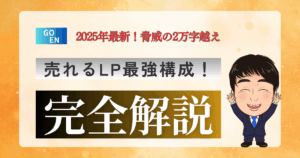
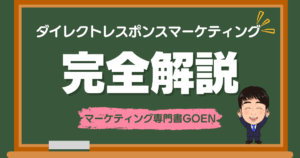


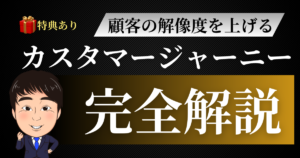
コメント