どうも!あきです。
今回は売れるLP(ランディングページ)の作り方について完全解説していきます。
実際に事業相談をしていて、必ずと言っていいほど、聞かれるのが「どんなLPを作成すればいいですか?」という質問です。
中にはホームページとランディングページが一緒になっちゃっている方もいるので、大きな落とし穴にハマっちゃいそうだな!と感じました。
そこで今回は、この記事一本で、「売れるLPの最強構成」を完全解説していきます!
これからLPを作ろうとしている初心者の方から、既に運用している上級者の方まで、「最強のLPの作り方とその構成」の全てを、この記事にギュッと詰め込みました。
私自身、これまで数多くのLPに関するご相談を受けてきましたし、この記事で解説する内容を実践することで、皆さんのLPが確実に成果を出すページへと進化すると確信しています。
この記事を最後まで見れば、LPとHPの明確な違いが分かり、あなたのビジネスの目的達成に必要な「売れるLPの具体的な構成と流れ」を完全に理解することができます。
これからあなたのLPが、ただのウェブページではなく、強力な「セールスツール」365日働いてくれる最強の営業マンへと変化させていきましょう。
それでは見ていきましょう。
今回の記事の動画はこちら↓チャンネル登録して効率的にマーケティングを一緒に学びましょう!
動画の方が記事よりも「例え」を多く入れて話しているので、理解しやすいと思います。
そもそもランディングページとは?
まず、ランディングページを日本語にすると「着地するページ」という意味になります。
つまり、ランディングページとは、広告や検索結果などからユーザーが最初に訪れる(着地する)特定のウェブページのことです。
LPの主な目的は、商品購入や資料請求、問い合わせといった特定の行動(コンバージョン)をユーザーに促すことに特化しているページです。
一般的なウェブサイトが複数ページで構成されているのに対し、LPは通常1ページで完結し、他のページへのリンクを極力減らすことで、訪問者の注意をLPページに集中させます。
ランディンページは目を引くデザインと、明確な行動を促すボタン(CTA)が特徴的な、セールス色の強いページとも言えます。
ランディングページとホームページの違いを明確に理解しよう
ここでランディングページとホームページは一緒ですか?という声が聞こえてくるので、解説します。
結論から言うと、ユーザーが見るウェブページという点においては同じですが、LPとHPの目的と設計は大きく異なります。
LPがお客様に特定の行動を促す「攻めのページ」であるのに対して、HP(ホームページ)は多角的な情報を提供する「受けのページ」だと考えると分かりやすいかと思います。
もう少し詳しく説明しますね。
LPとHPの違いを以下の5つのポイントから解説します。
1、目的の違い
2、構成とページ数の違い
3、ターゲットの違い
4、集客方法の違い
5、デザインの違い
順番に解説していきます。
目的の違い
ランディングページ(LP)は、商品購入、資料請求、お問い合わせ、セミナー申し込みといった、特定の行動(コンバージョン)をユーザーに促すことに特化してデザインされています。
一方、ホームページ(HP)は、商品やサービス、企業情報、IR情報など、あらゆる情報を提供し、企業の認知度向上やブランドイメージ確立が主な目的となります。
攻めか?受け身か?みたいな違いがLPとHPにはあります。
構成とページ数の違い
LPは、通常1ページで完結し、他のページへのリンクを極力排除しています。
なぜなら、そのページで商品の購入やサービスを申し込んで欲しいので余計なページを見に行って欲しくないからです。
LPページはユーザーの注意をコンバージョンへ集中させることを目的としています。
LPは縦長で1枚のレイアウトになっていることが特徴で、「資料請求する」「購入する」といった明確なCTA(行動喚起)ボタンが目立つように配置されています。
海外では縦長ではなく、短いLPの方が購入率が高いというデータがあります。
日本でも近年では長いLPの方がいいのか?短いLPの方がいいのか?スワイプLPの方がいいのか?みたいな論争がありますが、これに関しても私なりの明確な答えがあるので、このまま記事を読み進めてください。
少し脱線しましたが、HPの方では企業全体を幅広くPRするため、複数のページで構成されており、多様な情報を提供し、ユーザーはサイト内を自由に回遊できるようになっています。
HPの方は回遊率を高めて自社への理解を深めてもらうことを目的とするので、自然と構成やページ数が変わってきます。
ターゲットの違い
LPは、特定の商材やキャンペーンに合わせた見込み顧客という狭い層に絞り込み、そのニーズに特化した訴求を行います。
HPは、顧客だけでなく、投資家や求職者など、あらゆるステークホルダー(利害関係者)がターゲットとなります。
集客方法の違い
LPは、リスティング広告やSNS広告など、Web広告からの流入が主となります。
広告費を投じることで、短期間での集客とコンバージョン獲得を目指します。
HPは、検索エンジンでのSEO対策によって自然検索からの流入を増やし、長期的な集客を目指します。
デザインの違い
LPは、ユーザーの興味を一気に引きつけ、コンバージョンへと導くためのセールス色の強い、目を引くデザインになっていることが多いです。
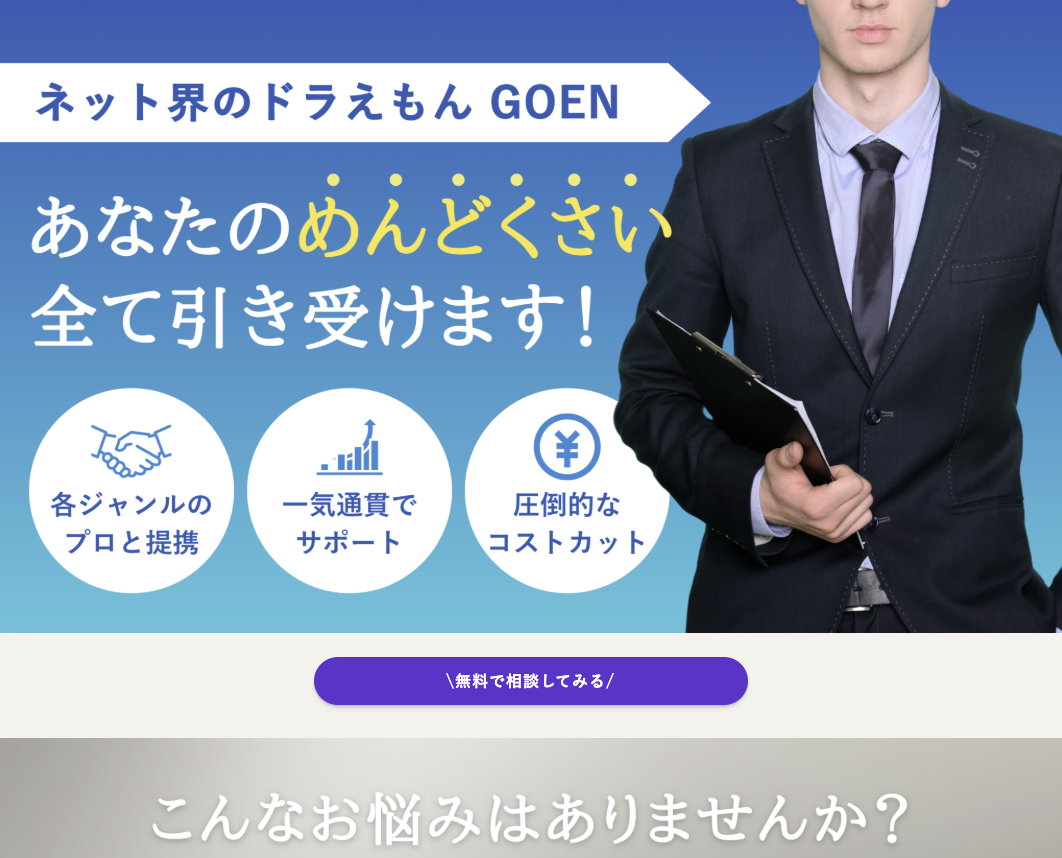
一方、HPは誰にでも受け入れられるようなオーソドックスなデザインが好まれ、企業イメージを表現しつつ、情報を見つけやすいデザインになっています。

LPとHPは分けないとダメなのか?
結論から言うと分ける必要はありませんし、LPにHPの機能を持たせることも可能です。
長いLPの中に会社情報なども入れることで、LPだけどHPとも言えるようね!みたいなページになっている会社さんもあります。
他にも、私のこのウェブサイトはホームのページは1枚のLPになっています。
良かっら見てみてください。
↓
そこではコンサルサービスへの申し込みを促した設計になっていますが、他のページではHPのように複数ページを用意して、回遊率を上げる工夫がなされています。
こんな感じですね。
↓
なので、正確にLPとHPを区別して分けなくても、私のサイトのようにハイブリッドモデルを作ることも可能です。
このような設計から運用まで私の方で一気通貫でお任せいただくことも可能です。
また「設計だけお願いしたい!」と言うような要望も可能なので、お気軽にご連絡ください。
LPページの構成はセクションで捉えよう!
今回紹介する売れるLPの構成を理解する上で必ず知っておいてほしいことがあります。
知っておいて欲しいポイントは以下の12個です。
1、ファーストビュー
2、顧客の悩みに共感する
3、どんな価値やメリットをお客さんに提供できるのかを全て伝えること
4、問い合わせ方法を入れること
5、お客様の声・導入事例・実例を入れる
6、選ばれる理由や特徴を明確に伝えること
7、あなたの人柄やスタッフ紹介を入れること
8、テキストだけでなく、動画セクションも検討しよう
9、価格の表記は松竹梅で考えよう
10、フッターセクションについて
11、購入後の流れをイメージできるくらい細く伝えよう
12、リスクリバーサルも検討しよう
このポイントを一つのセクションだと考えてください。
このセクションをどのように組み合わせるかを考えて1枚のLPを構成します。
例えば、店舗系の場合は必要な要素は以下だなと思ったとします。
1、ファーストビューのセクション
2、顧客の悩みに共感するセクション
3、お客様の声・導入事例・実例を入れるセクション
4、あなたの人柄やスタッフ紹介を入れるセクション
5、価格の表記は松竹梅で入れるセクション
6、フッターセクション
そうしたら、これをパズルのようにどの順番がいいかな?と組み合わせていくイメージです。
そして、このパズルの大枠が完成したら、その各ポイントの中身を肉付けしていきます。
肉付けする考えた方などはこれから詳しく説明していきます。
ここでは、各ポイントはパズルのピースだと考えてください。
全て入れてもいいですし、必要なピースだけを取って、いい感じの順番で構成することも可能です。
私のLPを見てもらえればすぐに理解できると思います。
最初にファーストビューのセクションがあって、次にお客様のお悩みを代弁する共感セクションがあってと言うようにセクションごとにLPを分解して見ていくと理解しやすくなります。
私のLPページはこちら
それでは、売れるLPの構成を詳しく見ていきましょう。
売れるランディングページの作り方|成果へ導く全体構成と流れ
まずLPを作成する前にお客様像を想像することから始めましょう。
多くの方はLPのファーストビューが大事!ベネフィットやオファーが大事と言っています。
もちろん!LPの要素で考えれば、それらは非常に重要です。
ですが、それらを考える前段階にまず始めは目を向けて欲しいです。
それは、検索しているユーザーのニーズにあったLPと今すぐ客とそのうち客で分けてLP作ると言うことです。
今何を言っているか理解できなくても、順番に丁寧に解説していきますので、安心してください。
まず初めに検索しているユーザーのニーズにあったLPを作成すること!からご説明します。
ユーザーが求めている言葉(キーワード)とLPの内容が合致しないと、どれだけ良いサービスでもスルーされてしまい、反応率は必ず落ちてしまいます。
例えば、「ラーメン 池袋」と調べているユーザーは池袋でラーメンを食べられるお店を探しています。
もし、そのニーズにピッタリなLPが表示されたら、どうでしょう?問い合わせがもらえる可能性がありますよね。
でも、「ラーメン 池袋」と調べている人に対してスパゲッティのLPが出てきたらどうでしょう?ラーメンを探している人にスパゲッティのLPを見せても反応が悪そうですよね。
考えてみれば、当たり前のことですが、ネットの世界になるとこれを実際にやって反応が悪い!と言っている方が非常に多い印象です。
検索しているニーズと違うLPを表示していれば、ユーザーは瞬時に「この情報はなんか違うな!別のページ見よう!」となってしまうからです。
つまり、ユーザーのニーズをしっかりと捉えた上で売れるLPの要素や構成を理解しないと全く意味がないよ!と言うことです。
このようなミスマッチが起きないようにLPのファーストビューでこのページはあなたに関係のあるページだよ!と一瞬で理解させるためにファーストビューが大事と言われているのです。
ここまでちゃんと本質を理解しておくことが売れるLPを作る上では非常に重要になってきます。
それともう一つ必ず知っておくべき前提条件があります。
それはユーザーニーズの中にも「今すぐ客」と「そのうち客」の二つのパターンがあると言うことです。
今すぐ客はすぐに商品やサービスを購入したい人たち、そのうち客は緊急性を感じていなくて、いつか買おうかな?と考えている人達です。
それぞれの顧客タイプで求める情報や行動が異なるため、コンテンツを分けて提供することが重要です。
LPは1つ用意して終わりではありません。
複数のLPを作成し、「どこのお客様像に焦点を当てるのか?」このような考え方が重要です。
例えば、「今すぐ客」と「そのうち客」を、病院や旅行のケースに置き換えて説明します。
今すぐ客の例:病院の場合
- 例えば、急な腹痛やケガで「今すぐ診てもらいたい」という患者さんです。
- この場合、患者さんが求めるのは「すぐ診察してもらえるか」「今開いているか」「待ち時間はどれくらいか」といった、緊急性の高い情報です。
- 病院側としては、「当日診療可」「夜間・休日診療」「待ち時間の目安」など、すぐに利用できることを強調した案内が必要です。
そのうち客の例:旅行の場合
- 一方で、「来月の連休に旅行を計画したい」と考えている人は、じっくり比較検討したいタイプです。
- この場合、旅行者が重視するのは「予約のしやすさ」「キャンセルポリシー」「早割の有無」「プランの選択肢」など、計画的に選べる情報です。
- 旅行会社としては、「事前予約のメリット」「豊富なプラン」「早期割引」など、余裕をもって選べることをアピールするLPにするべきです。
このように、「今すぐ客」はスピードや即時対応を重視し、「そのうち客」は選択肢や計画性を重視するため、それぞれに合わせた情報提供やサービス設計がLPには求められます。
少し前置きが長くなりましたが、非常に重要な要素なので、ご説明しました。
お客様の検索ニーズにLPを合わせることと、今すぐ客かそのうち客かのどちらに焦点を当てるのか?
この二つの前提条件を理解できた上で、売れるLPの要素や構成を見ていきましょう。
ファーストビューはめちゃくちゃ大切
ファーストビューとは、ユーザーがウェブサイトにアクセスした際、スクロールせずに一番最初に目にする画面のことです。
では、なぜファーストビューがそれほどまでに重要なのでしょうか?
Microsoftの調査によると、ユーザーは最初の10秒で「続きを読むか、離脱するか」を判断すると言われています。
個人的には10秒も無くて3秒くらいで「見るか・見ないか」決まる印象です。
つまり、このファースビューでユーザーの心を掴めなければ、せっかく集客した見込み客のほとんどが、肝心な情報にたどり着く前に去ってしまうのです。
なので、ユーザーに「自分は正しいページに来た」「このページは自分の課題を解決してくれそうだ」と確信させるための、最初にして最大のチャンスなのです。
では、このファースビューを明確にするにはどするべきなのか?
以下の3つの質問に明確に回答できるようにしましょう。
1.「どんなサービス・商品を扱っているのか?」
- 例えば、あなたがオンライン講座を開いているなら、「このページを見れば、どんな講座が受けられるのかがすぐに伝わる」ことが大切です。
- また、無料体験や限定キャンペーンを実施している場合は、「今だけの特典が何か」が一目で分かるようにしましょう。
- LINE登録やメルマガ登録を促したいなら、「登録すると何が得られるのか」がファーストビューで直感的に伝わるように設計します。
2.「利用者の暮らしや仕事がどう良くなるのか?」
- そのサービスや商品を使うことで「どんな悩みが解決できるのか」「どんな未来が待っているのか」を、簡潔なキャッチコピーやイメージで示しましょう。
- 例えば、「このオンライン講座で、未経験からプロのスキルが身につく」「この掃除機で、毎日の家事がもっとラクになる」といった、利用後の変化やメリットを明確に伝えます。
3.「どうやって申し込めばいいのか?」
- 申込方法や次のアクションがすぐに分かるように、目立つボタンやリンク(CTA)を配置します。
- 例えば、「今すぐ無料で登録」「電子書籍をダウンロードする」「セミナーの詳細を見る」など、訪問者が迷わず行動できる表現にしましょう。
- ボタンの色や配置も工夫し、ファーストビューで「ここを押せばいい」と直感的に分かるようにします。
このように、「何を提供しているのか」「どんな良いことがあるのか」「どう行動すればいいのか」を、見た瞬間に伝わる形に言い換えることで、より多くの人に興味を持ってもらいやすくなります。
もし既にLPがある場合は、第三者のあなたのサービスを何も知らない人に以下の質問をしてみてください。
- 「このページで何を扱っているのか、すぐに理解できるか?」
- 「このサービスや商品を使うと、自分の暮らしや状況がどう良くなるか、瞬時にイメージできるか?」
- 「申し込みや購入の手順が、見ただけで明確に分かるか?」
これらのポイントがクリアに伝わるようにファーストビューをブラッシュアップすることで、ページの成果を大きく伸ばすことが期待できます。
顧客の悩みに共感すること
売れるランディングページに必要な要素2つ目の重要なポイントは、まさに「顧客の悩みに共感する」ことです。
ユーザーがLPに訪問するのは、何らかの課題や悩みを解決したいと考えているからです。
そして、彼らはLPのページをわずか約3秒で読み進めるか、離脱するかを判断します。
この最初の数秒で、「私の悩みを理解してくれている」と感じてもらえなければ、せっかく訪れてくれたユーザーはすぐに去ってしまうでしょう。
顧客に「自分ごと化」してもらうことで、「このページは自分の課題を解決してくれそうだ」と確信し、LPを読み進める強い動機が生まれるのです。
「このページは自分のためのものだ」「この人は自分のことを分かってくれている」と感じることで、初めて深い信頼関係が構築されます。
では、具体的にどうすれば顧客の悩みに共感し、読み手の心を掴めるのでしょうか?ポイントは3つです。
1、「ユーザー目線」で課題を提示するキャッチコピーを作ること!
2、「共感」からの「未来」を示すメッセージを作ること!
3、「信頼性」で共感を確信に変えること!
順番に解説していきます。
1.「ユーザー目線」で課題を提示するキャッチコピーを作ること!
- 単に商品の特徴を羅列するのではなく、ユーザーが抱えるであろう具体的な悩みや問題を、問いかける形で提示します。
- 例えば、スキンケア用品であれば、「私はまだ大丈夫なんて油断してませんか?20代のケアが10年後の肌を左右します」みたいな感じで、ユーザーがまだ意識していない潜在的な不安に訴えかけたりすると効果的です。
- サプリメントなら、「鉄分不足を感じてませんか?」と顕在化している課題を突いたりすると効果的です。
- 毛穴ケア商品では、「毛穴の黒ずみ・開きが気になる、そんなお悩みありませんか?」と明確な悩みを提示することで、ユーザーは「まさに私のことだ」と強く感じ、読み進めるモチベーションが生まれます。
2.「共感」からの「未来」を示すメッセージを作ること!
- 悩みに共感した後は、その悩みが解決された理想の未来や、商品やサービスを導入することで得られるベネフィットを具体的に提示します。
- 例えば、あるLPでは「サービスを導入した後、ランディングページを継続的に見直して改善することで、申し込みや問い合わせの数を最大限に増やせます」と、利用後に得られる未来を具体的な成果と共に分かりやすく伝えています。
- これは、ユーザーが抱える問題が解消され、快適な状態になる「快楽を得られる」アプローチとして効果的です。
- 他にも「自分自身も元々、お客さんと同じことで悩んでいたんですよ」とか、「このお客さんの悩みと同じ経験をしてきた人間なんですよ」といった、共感できるご自身のストーリーを盛り込むことで、顧客からの信頼度が格段に向上します。そこからどう変わってどんな未来に行けたかまでをセットで書くと良いでしょう。
3.「信頼性」で共感を確信に変えること!
- ハロー効果を活用し、突出した実績や、信頼できる第三者の評価を提示することで、共感を確信に変えます。
ハロー効果とは一部の目立つ特徴や印象に引きずられて、全体の評価が歪められてしまう心理現象です。例えば、外見が良い人を「性格も良い」「仕事もできそう」と感じたり、有名大学出身というだけで「能力も高い」と思い込んだりするケースがこれにあたります。 - 他にも、「〇〇賞受賞!」や「お客様満足度98%!」といった権威付けは、ユーザーに安心感を与え、心理的なハードルを下げる効果が期待できます。
ユーザーは、単に成功している人の話を聞きたいわけではありません。
「この人は自分の悩みや苦労を分かってくれるんだな」と感じられる、実際のビジネスや現場で苦労を経験し、成果を出してきた人の話にこそ、耳を傾けたいと思うものなのです。
どんな価値やメリットをお客さんに提供できるのかを全て伝えること
売れるLPにおいて3つ目の重要な要素は、ズバリ「価値の提案」です。
ファーストビューで提示したメリットや、顧客の悩みに共感した後に、実際に「お客様は何を手に入れることができるのか?」「どんな未来が手に入るのか?」を明確に全て伝えることが重要です。
多くのLPでは、提供できるメリットを一つに絞ったり、あるいは「これくらいでいいだろう」と考えて情報を削ったりしがちです。
しかし、ランディングページを見に来る人は、「購入したい」という気持ちを持って、その決断を後押しするための情報を探しています。
購入の意思があるからこそ、詳細な情報を求めています。
そのため、あなたの提供する商品やサービスによって得られるベネフィット、結果、変化といった情報をしっかりとLPの中で提供することが、購入を迷っているお客さんの背中を押すためには不可欠なのです。
例えば、英会話スクールのサービスを販売する場合を考えてみましょう。
単に「英語が話せるようになります」と伝えるだけでなく、以下のような複数の具体的なメリットを提示します。
- 「初心者でも3か月で日常会話ができるようになります」
- 「自宅にいながらプロの講師とマンツーマンでレッスンを受けられます」
- 「海外旅行やビジネスで自信を持って英語を使えるようになります」
このように、一つの利点だけに絞らず、利用者がサービスを通じて得られるさまざまなメリットや変化を、箇条書きなどで分かりやすく伝えることが大切です。
極論を言えば、LPに必要な情報が全て詰まっていて、お客様からの質問が何も浮かばないくらいの情報量を詰め込むことが正解です。
今はLPにチャットボットなどを埋め込んで、すぐに質問に回答できるような体制をとることはできますが、基本的にLPの中だけでお客様が納得して、購入や申し込みまで完了できるLPを作らないといけません。
お客様から質問が来た時点で、そのLPにはまだまだ改善の余地があるとも言えます。
なので、長いLPか短いLPかはお客様のお悩みを全て解決できているのであれば、長くても短くてもどっちでもいいと私は考えています。
問い合わせ方法を入れること
売れるランディングページ(LP)の最終目標は、訪問者に明確な行動を促し、コンバージョンを達成することです。
そのためには、問い合わせ方法を限りなくスムーズで、ストレスのないものにすることが極めて重要です。
ユーザーが「今すぐ解決したい」と感じても、問い合わせのステップで戸惑いや不安を感じれば、簡単に離脱してしまいます。
多くのユーザーは、商品やサービスに関する「購入しなかった場合の損失」や、支払い方法、契約内容などに対する不安を少なからず抱えています。
これらの疑問や不安を解消できなければ、お客様は行動を躊躇します。
また、残念ながら、入力フォームでの離脱は非常に多く、せっかく興味を持ったユーザーを逃してしまう大きな要因となっています。
その理由に訳のわからないサイトに自分の情報を入力するのが怖いと思っている方や手間だと感じる方が多いからです。
入力フォームへの誘導ではなく、LINEにワンクリックで誘導を促したり、見込み客がどんな人でどんな問い合わせフォームを設置することが最適解なのかを模索するのも良いでしょう。
そんな時に使えるフレームワークがあります。興味がある方は以下の記事をご覧ください。(動画もあります!)
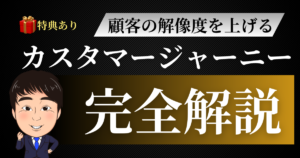
また、選択肢が多すぎると人は行動を回避する傾向があるため、シンプルで明確なゴールへと導く必要があります。
ユーザーが迷わず、安心して行動できる環境を整えることこそが、購入率や申し込み率向上の鍵となるのです。
では、具体的にどのように問い合わせ方法を最適化し、ユーザーの行動を後押しすれば良いのでしょうか?ポイントをいくつかご紹介します。
1.「よくある質問(FAQ)」で不安を先回りして解消する
ユーザーが抱くであろう疑問や懸念を、「よくある質問」の形で事前に提示し、解決しておきましょう。
これにより、ユーザーは問い合わせる前に自ら問題を解消でき、安心して次のステップへ進めます。
もし質問が複雑でLP内で簡潔に説明できない場合は、「まずはお気軽にお問い合わせください」といったメッセージで、問い合わせへの心理的ハードルを下げる工夫も有効です。
2.「入力フォーム」の最適化(EFO)を徹底する
フォームでの離脱を防ぐため、EFO(Entry Form Optimization:入力フォーム最適化)は必須です。
入力項目を必要最低限に絞り込むことが大原則です。「ふりがな」や「FAX番号」など、本当に必要な情報かを見直しましょう。
郵便番号からの住所自動入力や、フリガナの自動入力など、入力アシスト機能を積極的に導入し、ユーザーの手間を省きましょう。
入力エラーがあった際には、リアルタイムで分かりやすいエラーメッセージを表示し、ユーザーがスムーズに修正できるようにしましょう。
フォームから他のページへ遷移するリンクは極力設置しないでください。
ユーザーの集中を妨げ、離脱の原因となります。
最近では、チャットボットやWebチャットツールを併用することで、ユーザーの疑問を即座に解消し、問い合わせへのハードルを大きく下げる施策も効果的です。
3.多様な「問い合わせ方法」と「利便性の高い導線」を提供する
ユーザー層に合わせて、問い合わせの選択肢を増やすことも有効です。
例えば、若年層にはLINEでの問い合わせボタンを目立たせたり、高齢者層向けにはFAX注文用の用紙ダウンロードボタンを設置したりする事例もあります。
私のお問い合わせページもBtoB向けにはコンタクトフォームを用意し、BtoC向けにはLINE追加を誘導しています。
正直、どっちかでもいいとは思いますが、BtoB向けにLINE追加だけを促すと「メールの問い合わせフォームがあれば、問い合わせしたんだよな〜」みたいなお客さんを少しでも取りこぼさないように両方用意しています。
一度構築してしまえば、あとは比較的放置していても大丈夫なので、可能ならお客様の利便性が最も高いお問い合わせ先を用意しましょう。
他にも「フォーム一体型LP」を導入することで、ページ遷移なく1ページで閲覧から購入までを完結させることができ、ユーザーのストレスを大幅に軽減し、コンバージョン率が約1.5~2.5倍に向上する可能性があります。
EC系の人の場合はAmazonやApple payなんかと連携しておけば、ユーザー登録不要で決済まで持っていけるので便利です。
ShopifyではAmazon連携できなくりました!
4.「CTA」を最適化し、行動を後押しする
「資料請求する」「購入する」といったCTA(Call To Action:行動喚起)ボタンは、常にユーザーが見つけやすい位置に、明確に表示してください。
ボタンと背景のコントラストを意識したり、余白をうまく活用したりして、目立つデザインにしましょう。
ボタン周辺に「45秒で完了します」「半額は〇月〇日まで!」のような、登録の簡便性や緊急性を伝えるコピーを入れることで、ユーザーのクリックを強力に後押しできます。
また、「無料体験する」のようにユーザーの心理的なハードルを下げる文言も効果的です。
画面スクロールに追従するフローティングCTAや、ページ離脱時に表示される離脱防止ポップアップでクーポンなどを訴求し、離脱しかけたユーザーを引き留め、コンバージョンに繋げることもできます。
お客様の声・導入事例・実例を入れる
売れるランディングページに不可欠な要素として「お客様の声」や「導入事例」、そして「実績」といった、第三者からの信頼できる情報が非常に重要です。
あなたも何か商品を購入する時、必ずレビューを見て購入するかを検討しているのではないでしょうか?
実際にそのような調査がたくさん行われていて、およそ8割の人はレビューを見て商品やサービスを申し込むかの判断材料にしていると言われています。
その理由は単純で、人間は失敗したくないと思うからです。
先に買っている人がどんな評価をしているのか?自分はその商品を購入して失敗したくない!と言う心理が働くので、レビューを多くの方が参考にしているのです。
店舗と違ってウェブサイト上では商品やサービスを直接体験できません。
なので、ユーザーは、「本当に効果があるのか」「自分に合うのか」といった「効果が出なかったらどうしよう」という不安、いわゆるマッチングリスク意識を少なからず抱えています。
このような時に、お客様の声などのレビューは、非常に現実味と安心感を与えることができます。
さらに、多くの人が利用しているという事実を示すことで、「バンドワゴン効果」が働き、「みんなが選んでいるなら安心」という心理が働きます。
つまり、ユーザーの潜在的な疑問や不安を先回りして解消し、心理的なハードルを下げることで、「購入する正当な理由」を与え、行動を強力に後押しするのです。
お客様の声をLPに入れた方がいいことは何となく分かっていたけど、本質的にはちゃんと理解していなかった方も多いのではないでしょうか?
このようにお客様の声を入れる理由が明確になることで、どんなレビューを入れるのが効果的なのかも見えてきます。
ここからは具体的にどのように「お客様の声」や「導入事例」を活用すれば、その効果を最大化できるのかについて詳しく見ていきましょう。
効果的な「お客様の声」や「導入事例」を作成・活用するためのポイントは、以下の3点です。
1. お客様の「属性」を詳しく紹介する
2.「数値化」して具体的に伝える
3. 「ハロー効果」や「バンドワゴン効果」を応用する
順番に解説していきます。
1. お客様の「属性」を詳しく紹介する
単なるコメントだけでなく、氏名、住所(少なくとも都道府県)、年齢、会社名、など、可能な限り具体的に記載しましょう。
昔はイニシャルでもOKでしたが、最近はサクラでしょ!って思われる可能性が高いのでイニシャルは怪しいのでやめた方が無難です。
他にも、本人の顔写真などがあれば信憑性が格段に高まります。
最近の流行りだと、動画でレビューを投稿してもらうのが一番効果が高いです。
ビフォーアフターを動画で紹介したり、施術を受けた前と後でどんな風に変化したかを対談形式でアップする良いでしょう。
例えば、ヘアケア商品であれば、「朝と夜のケアでこんなに水分量がアップ」といった具体的な変化を示す声、サプリメントであれば、「続けるだけで集中力もUP」といったメリットを紹介してみましょう。
スキンケア用品であれば、「1回の使用でこんなにつるつるに!」のような効果を、利用者の具体的な背景と共に紹介することで、ユーザーは利用後の自分をより鮮明にイメージできるようになります。
これらの情報を文字だけでなく、動画でLPに埋め込むことができるのであればした方が良いでしょう。
それも一人の属性ではなく、会社員の方のレビュー、主婦の方のレビュー、学生さんからのレビューなど、属性がバラバラの方が、同じ属性の人から共感を得やすいのでより効果を発揮します。
2.「数値化」して具体的に伝える
「スゴイ」「うれしい」「改善された」といった曖昧な表現ではなく、「〇〇大学に78名合格!」のように具体的な数字を用いて効果を伝えましょう。
数字が難しい場合は、「毎朝鏡を見るのが楽しみになりました」のように、どのようにスゴいのか、うれしいのかを鮮明にイメージできるように、具体的に伝えることが重要です。
「累計販売数100万本突破」「Youtubeで100万再生突破!」といったデータ提示は、「バンドワゴン効果」を強力に働かせ、信頼性を高めます。
3. 「ハロー効果」や「バンドワゴン効果」を応用する
「圧倒的な実績」や「著名人・専門家の推薦コメント」を提示することで、その権威や信頼性が商品・サービスに乗っかり、「この商品は信頼できる」と感じさせることができます。
このテクニックは借景とも呼ばれています。
私の動画でも有名なマーケッターが本で紹介している内容を私が紹介することで、私に実績がなくても、その本の著者の実績を借りるテクニックのことです。
例えば、人気俳優が広告塔となることで、その企業の製品が誠実でクリーンな印象を与えることがあります。
これは人気俳優のイメージを借景しているような状況です。
他にも、複数の体験談を掲載することで、「たくさんの人に選ばれている」という安心感を与え、「バンドワゴン効果」を狙うこともできます。
これにより、「自分も試してみよう」という行動を促すことができます。
既にお客様がいて、素材がある方やLPを既に作成している方は「お客様の声」や「導入事例」に、より詳細な「属性情報」や「具体的な数値」が盛り込まれているかを確認してください。
もし不足しているなら、既存顧客へのアンケートやインタビューを通じて、具体的なエピソードやデータを集め直すことを検討しましょう。
選ばれる理由や特徴を明確に伝えること
ここでいう選ばれる理由はと言うのは、競合にはない「独自性」と「強み」を具体的に提示しましょう!と言うことです。
あなたの製品・サービスが、他の類似品と比べて何が特別なのか、どんな「競合優位性」があるのかを明確にします。
例えば、「パッケージもサスティナブルに」や「肌にやさしい成分でできています」、「こんな成分使ってます」 のように、具体的な製品特性やこだわりを伝えて見ましょう
お客様に私たちを選ぶべき理由は〇〇だからです!と明確に伝えるセクションを作っても良いでしょう。
あなたの人柄やスタッフ紹介セクションを入れること
LPには、サービスを提供する「人」の顔が見えるようにしましょう。
他にも、スタッフさんがいるのであれば、スタッフさんの紹介もLPの中に入れましょう。
でも、具体的に何を書けばいいのか迷ってしまいますよね?
安心してください!詳しく解説していきます。
このセクションで伝えるべきは、あなたのサービスの品質はもちろんですが、それ以上に「提供する人の人柄」です。
人柄をアピールすることで、お客様はサービスと自分との関連性をより強く感じ、心理的な距離が縮まります。
もし、LPにスタッフの顔が見えない、あるいは事務的な情報しかない場合、お客様は「どんな人が来るのか分からなくて不安だな…」と感じ、最終的な決断を躊躇してしまう可能性があります。
せっかくサービスに興味を持ってもらっても、最後の最後で「人」への不安がボトルネックとなり、離脱に繋がるのは避けたいですよね。
「逆に、笑顔の写真と共に、親しみやすいスタッフ紹介があれば、お客様は「この人なら安心して任せられそう!」と強く共感し、期待感と信頼感を持って、次の行動へと進むことができます。
では、顧客に響く「スタッフ紹介」をどう作成すれば良いのか?気になりますよね。
当たり前ですが、笑顔の写真を掲載し、簡単な自己紹介やプロフィールを添えましょう。
そして、最も重要なポイントは、仕事内容に直接関係なくても構わないので、スタッフの「趣味」や「休日何をしているか」などを書くことです。
「例えば、2児のパパです。子供と遊ぶのが大好きです」 や、「キャンプが好きで、休日もよくキャンプに行きます」といった情報で十分です。
明確にこれがなぜ大事なのか?と言うことは言語化できませんが、スーパーの野菜などにも「私たちが作りました!」と言う生産者さんの顔写真付きの野菜販売を目にした方も多いかと思います。
要するに、どんな人が作ったのか?店舗系ならどんな人がいるのか?人柄を前面に出すことは「安心感」に繋がります。
他にも、意気込みなどを加えるのも良いですが、趣味だけでも十分効果が期待できます。
なので、あなたのサービスを支えるスタッフの「人柄」を伝え、お客様に安心と信頼を提供しましょう!
細かいことですが、これが顧客の不安を払拭し、成約へと導くための強力な要素となります。
テキストだけでなく、動画セクションも検討しよう
実は、ランディングページの成果を劇的に変える隠れたキーポイントがあります。
それは、「動画セクションをLPの中に入れることです!」
ランディングページにおいて、テキストや静止画だけでなく、動画コンテンツを導入することは、ユーザーの理解度とエンゲージメントを飛躍的に高め、結果としてコンバージョン率を劇的に向上させることができます。
実際に動画をLPに入れてから、コンバージョン率が3倍になった事例も確認しています。
また、現代のWebユーザーは、長文のテキストを読み飛ばす傾向にあります。
動画は、この「読まない」ユーザーの習性に対応し、情報を効率的かつ効果的に伝える手段となるため、ユーザーがページから離脱するのを防ぎます。
他にも動画を入れることの利点としては、静止画よりもユーザーの目に留まりやすく、特に商品やサービスが実際に利用されるシーンや、複雑な機能など、静止画では伝えにくいニュアンスやプロセスを分かりやすく、感情に訴えかけた形で表現することができます。
例えば、
強力な泡でお皿の汚れが落ちる食器用洗剤を販売する場合、言葉で説明するよりも、実際に泡が大量に出て汚れが綺麗に落ちていく様子を見せた方が、圧倒的に早く、そして強くメッセージが伝わります 。
それもそのはずで、動画はテキストの500倍の情報量があるとも言われています。
人間の8割の情報は視覚的、つまり目から入ってきます。
生物学的にも、テキストよりも動画の方が圧倒的な情報量を伝えることができるのは明白です。
動画は単なる補足情報ではなく、顧客の理解を深め、購買意欲を高めるための戦略的な要素として位置づけることが重要です。
じゃーどういう動画がいいのか?についてはここで説明すると長くなるので、別途記事を用意したいと考えています。
重要なポイント以下の3つです。
1、台本力
2、演者力
3、編集力
です。
詳しく知りたい方は、一度無料相談の方に来ていただければ、相談に乗ります。(※セールスなし)
お問い合わせ
価格の表記は松竹梅で考えよう
ランディングページにおいて、複数の価格プランを提示する際、「松竹梅の法則」を意識して価格表記を最適化することが、ユーザーの意思決定を促し、最も推奨したいプランへのコンバージョン率を飛躍的に向上させるためのテクニックとなります。
なぜ松竹梅の法則が、LPの価格戦略において有効なのか?詳しく説明していきます。
ちなみに、松竹梅が作れるなら作った方がいいですが、販売する商品やサービスによっては3種類の価格設定が難しい場合は必ずしも作る必要はありません。
では、なぜ私が松竹梅を推奨するのか見ていきましょう
人間は、複数の選択肢を提示されたときに、極端な選択(最も高価なものや最も安価なもの)を避け、中間的な選択肢を選ぶ傾向があります。
この心理的な特性は「極端の回避性(またはゴルディロックス効果)」と呼ばれ、多くの購買行動で観察されています。
松竹梅の法則は、この人間の本質的な行動パターンを巧みに利用します。
松竹梅の法則をLPの価格表示に応用することで、最も購入してほしい「竹」のプランが、ユーザーにとって「最も合理的で、バランスが取れており、価値のある選択」だと自然に感じさせることができます。
これにより、ユーザーは深く悩むことなく、推奨されるプランへとスムーズに誘導されます。
選択肢が多すぎると、ユーザーは決定回避の法則により、何も選ばずに離脱してしまう可能性があります。
松竹梅のように3つの明確な選択肢に絞り、その中でも「竹」を推奨することで、ユーザーは選択のストレスを感じにくくなり、スムーズに購入プロセスへ進むことが期待されます。
特に最近だと生成AI系のサブスクリプションのページを見てみてください。
ほとんが松竹梅の設計になっていることに気がつくかと思います。
このように、最高の「松」プランと最低の「梅」プランを提示することで、推奨する「竹」プランが、価格と価値の両面で誠実な提案であるという印象を与え、ユーザーの信頼感を醸成することにも繋がり、結果的に成約率が向上します。
フッターセクションについて
購入に直接必要のないリンクは、すべてフッターにまとめるべきだと考えています。
具体的には、会社概要、トップからの挨拶、プライバシーポリシーといった情報は、LPの最下部に配置し、決してLPの上部に置いてはいけません。
これから、なぜこれらの情報をフッターにまとめることが重要なのかについて解説します。
主に2つの明確な理由があります。
1.顧客の購買プロセスを妨げないため
LPの目的は、顧客に商品やサービスを購入してもらうことです。購入に直接関係のないリンクがLPの目立つ位置にあると、顧客の集中をそらし、購買への導線を妨げてしまう可能性があります。
フッターにまとめることで、見たい人が見れる場所にはありつつも、メインの訴求からは邪魔にならないという理想的な配置になります。
アフィリエイトなどでも、利益が上がるキラーページには余計な内部リンクを貼らないと同じことです。
要するに売り上げを上げることが目的のページなのであれば、それ以外のノイズは全て除去しましょう!と言うことです。
例えば、あなたがオンラインでサプリメントを販売するLPを運用しているとします。
LPの冒頭や途中に「会社概要はこちら」という大きなリンクがあると、せっかく商品に興味を持った顧客が、会社概要を見に行くことで購入の熱が冷めてしまう可能性があります。
しかし、これをフッターに配置していれば、「必要な人は見に行けるが、そうでない人はメインのセールスに集中できる」という状態を作り出せます。
細かいですが、このような細かい部分にまで目を向けてLPを改善していかないとLPO(ランディンページ最適化)はできません。
2.Web広告の審査に通りやすくなるため
これは実務的な非常に重要なポイントです。
フッターに会社情報やプライバシーポリシー、その他の関連ページへのリンクをまとめておくことで、Google広告、Facebook広告、Instagram広告などのWeb広告の審査に通りやすくなるというメリットがあります。
多くの広告プラットフォームは、広告主の信頼性や透明性を重視しており、これらの情報が明確に記載されていることを審査基準の一つとしているためです。
最近ではメタ広告も個人用アカウントでしっかりと運用歴がないと審査に合格しづらくなってきている印象です。
広告を回すだけのために解説した個人用アカウントでは広告掲載が難しくなってきています。
なので、広告を出す際にフッターに「会社概要」や「プライバシーポリシー」へのリンクがきちんと設置されていれば、「このLPは信頼できる情報が提供されている」と判断され、広告審査がスムーズに進む可能性が高まります。
 あき
あき可能性を上げる話であって、必ず審査に通るわけではありません!
購入後の流れをイメージできるくらい細く伝えよう
お客様は、購入ボタンを押した後に「次に何が起こるんだろう?」「本当に商品は届くのかな?」「サービスの利用はどう始まるんだろう?」といった漠然とした不安を抱くことがあります。
この不安が購入の障壁となってしまう恐れがあるので、具体的な「購入後の流れ」を入れることが有効です。
よく、購入後にメールで今後の流れを説明するメールが送られてきますが、購入前の段階でもしっかりと具体的な流れを提示しておきましょう。
私の広告運用丸投げプランのLPには「お申し込み後の流れ」と言うセクションがあるので、実物をみたい方はチェックしてみてください。
店舗系の人の場合は、駅から店舗までの動線を紹介したり、来店してからはどんな流れで施術が行われていくのか?
着替えが必要なのか?どんな感じのお部屋なのか?などなど。
お客様が知りたいと思われること、不安になるであろうことを先回りして答えてあげましょう。
リスクリバーサルも検討しよう
リスクリバーサルとは、顧客が商品やサービスの購入を検討する際に感じる不安やリスクを、売り手側が解消または軽減することで、購買を促進するマーケティング戦略です。
顧客が感じているリスクの代表例としては、以下です。
・金銭的リスク: 期待外れだった場合、お金を無駄にしてしまうのではないか?
・時間的リスク: 時間を無駄にしてしまうのではないか?
・心理的リスク: 後悔するのではないか? 周囲からどう思われるか?
・身体的リスク: 体に危害が及ぶのではないか?
このようなリスクを事業者側が肩代わりすることで、顧客の不安を解消し、安心して商品購入を決断できるようにする戦略です。
肩代わりする例としては以下になります。
1.返金保証:効果を実感できなければ返金
2.返品保証:商品が気に入らなければ返品可能
3.成果保証:目標達成をサポート
などなど。
他にもたくさんの肩代わりする手法があります。
リスクリバーサルについてもっと深く学びたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので、一読することをオススメします。
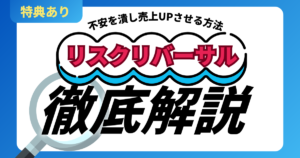
また、リスクリバーサルの事例と対策をまとめたレポートを、Lineの友達追加特典として無料で配布しています。
自分の事業で使える事例がないか?を探しながら見てみるのも良いかと思います。
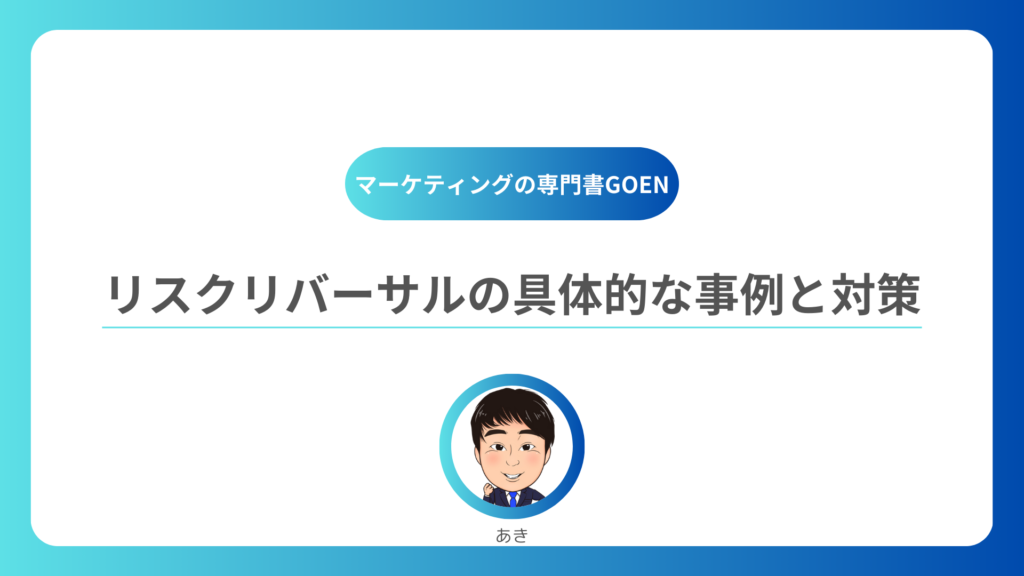

刺さるタイトルや限定オファーを提示しよう
LPを構成しているのは文字になります。
つまり、コピーライティングの能力がLPには必要不可欠です。
ただし、コピーライティングはとても奥が深くここで解説すると、とても長くなるので、LPの中でも重要なタイトルと限定オファーに絞ってお伝えしていきます。
ではなぜ、魅力的なタイトルや限定オファーを作る必要があるのか?
その理由は、魅力的なタイトルを作成することで、相手の興味を惹きつけ、LPをしっかり見てらもうためです。
限定オファーを作成する理由は、希少性や緊急性を訴求し、消費者の購買意欲を高めるためです。
現代社会は完全に情報過多なので、流し見しているユーザーの親指を止めて、あなたのコンテンツに注目させるために魅力的なタイトルを作成する必要があります。
つまり「おや!何だこれ?「見てみたい!知りたい!」このような欲求に刺さるタイトルを作成することが必要です。
ここで、人間の行動の8割は無意識に行われているというデータがあることをご存知でしたか?
自分が意識していると思っていることも、実は無意識で行われていたりします。
例えば、呼吸をしたり、ドアを開けたり、これらの行動を一々意識しないですよね。
このように人間の行動の8割は無意識で決定されているとも言われていて、刺さるタイトルを作成する上では、人間が無意識に反応してしまうキーワードというものが存在しています。
それが、期間限定、特別価格、セール、無料などなど。
このようなキーワードは意識していなくも、人が無意識に反応してしまう強力なキーワードなのです。
これらを上手にLPに含めることで、最強のタイトルやLPの文章をを作ることもできます。
実際0から自分でキーワードを考えるのはめちゃくちゃ大変ですよね。
なので、私が作成したスライド「刺さるキーワード集550を無料でプレゼント」します。
このスライドはキーワードを8つのカテゴリーに分けました。
1. 緊急性・限定性 – 今すぐ、限定、期間限定など
2. 効果・結果 – 最強、神業、革命的など
3. 秘密・特別性 – 秘密、裏技、非公開など
4. 感情・衝撃 – 驚愕、感動、衝撃など
5. 品質・価値 – 最高、極上、プレミアムなど
6. 簡単・手軽 – 一瞬、サクッと、誰でもなど
7.危険・注意 – 要注意、危険、悪用厳禁など
8. 無料・お得 – 無料、激安、お得など
なので、この中から自分のコンテンツに合うタイトルや限定オファーを見つけてもらえれば、すぐに魅力的な文言を作成できちゃいます!
受け取り方法は簡単、LINEを友達追加後「20秒で終わるアンケートに回答」して頂ければ、特典一覧ページのリンクを自動でお送りします。
そこから過去の特典も全てダウンロードできます。
ストーリーテリングを駆使する
ストーリーテリングとは、「物語を語って伝えること」を意味し、伝えたいメッセージやコンセプトを、印象的な体験談やエピソードなどの物語形式で聞き手に伝える手法です。
人間は物語が大好きな生き物です。
映画、ドラマ、神話、など何百年も前から物語は存在しています。
それだけ物語には人を惹きつける力があるのです。
なので、LPを1枚の物語形式で伝えることで、しっかりと読まれるLPを作ることができます。
では、どうすれば売れる物語形式のLPを作ることができるのか?
物語の一般的な構成は「起・承・転・結」ですが、売れるLPの基本構成は「結・起・承・転」が基本とされています。その理由として、ユーザーは何かの目的があって、LPをを見ています。つまり特定の商品やサービスを求めてLPに訪問しているため、まず最も知りたい情報を提示することが重要だからです。
ストーリーテリングを駆使する上で核となる部分は、どれだけ共感を呼ぶストーリーが作れるかです。
ビジネスオーナーの「想い」や背景を盛り込むことが非常に有効です。
苦労したポイントや開発秘話などは鉄板のストーリーテーリングとなっています。
他にも
・何故この事業を始めたのか?
・どのような課題を解決したいのか?
・顧客にどのような体験を提供したいのか?
これらのポイントを入れることで、LPに人間的な深みが加わり、訪問者との間に感情的なつながりを築くことが可能になります。
顧客は、単に提供されるサービスや商品の情報だけでなく、「どんな人が、どのような信念で」そのビジネスを運営しているのかを知りたいと考える傾向があります。
この「想い」が伝わることで、信頼感や共感を呼び起こし、結果として問い合わせや購買といった反応に繋がりやすくなります。
オススメの勉強法としてはクラウドファンディングのページを見てみるといいです!
多くのお金を集めていると言うことは、それだけ多くの人を動かしているとも言えます。
私が実際にクラウドファンディングで心動かされ、商品を購入した話は以下の記事で詳しく紹介しています。
クラウドファンディングの王道の成功事例を紹介しいます!
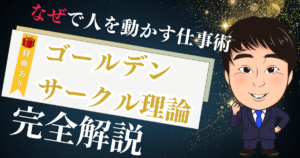
ぜひ事業に対する真摯な「想い」や、ビジネスを始めたきっかけ、あるいはその活動が社会にどう貢献したいかといった個人的なストーリーを盛り込むことを検討してください。
LP制作におけるその他重要なポイント
LP制作におけるその他重要なポイントは以下の4つです。
・スマートフォンの表示で必ず確認する
・TTPS(徹底的にパクる)を活用する
・「ダサいLP」でも十分成果が出る
・「数の暴力」で複数のLPを展開する
順番に解説していきます。
スマートフォンの表示で必ず確認する
現在、約8〜9割のユーザーがスマートフォンで検索しているため、LPを見る際は必ずレスポンシブデザイン(スマホモード)でも確認しましょう。
パソコンだとちゃんとしたデザインになっているけど、スマホで見ると崩れていることがあるので注意してください。

TTPS(徹底的にパクる)を活用する
LPをゼロから作ろうとせず、競合他社の良いLPから要素を「パクる(参考にする)」ようにしましょう。
もちろん、デザインや文言全て、丸パクリはダメです!
冒頭でも説明しましたが、LPをセクションと言うパズルで見ましょうとお伝えしました。
1つのLPから全て丸パクリするのではなく、あなたが良いと思ったセクションを複数のLPから必要なパズルを組み合わせる「いいとこ取り」が効率的です。
ここで多くの方は自分の参入しているジャンルのLPしか見ませんが、可能であれば異業種の広告を自分のLPに横展開できないか?と言う視点で他業種のLPを見ると思いもよらない発見をすることがあります。
また、LPではがないですが、メタ広告ライブラリーと言うメタ社がやっているサービスがあります。
ここでは過去から現在まで掲載されている広告が全て閲覧することが可能です。
昔から同じ広告を出していると言うことは、費用対効果が見合うだけの成果が出ているとも言えます!
なので、そこで使われている広告のデザインや文言を自分のLPに落とし込むことで、適当に作ったLPよりも成果が出る可能性を上げることができます。
「ダサいLP」でも十分成果が出る
プロが作った見栄えの良いLPよりも、素人がパッションを持って一生懸命作った「素人臭いLP」の方が反応が取れる場合があります。
プロが作ったLPに作り替えた結果、問い合わせのコンバージョン率が1/5に低下した事例もあります。
問い合わせ単価も素人LPの方が安くなる傾向があるため、見栄えよりも「伝わる」ことを重視しましょう。
ただし、業界や商品によっては綺麗なLPの方が好まれる可能性もあるので、素人ぽいLPを作れば成功すると言うことではありません。
必ずしも綺麗なプロが作ったようなデザインだから、売り上げが上がると言うわけではないと言うことです。
「数の暴力」で複数のLPを展開する
1つのLPが当たらなくても、複数のニーズに合わせたLPを量産し、どこかに当たることを狙います。
LPもそんなに安い物ではないので、何枚も作る発想がない方も多いですが、1枚作って当たるほど甘い世界ではありません。
何枚も作っては改善を繰り返して、当たるLPを作っていきます。
ジャンルにもよりますが、最初の「基盤となるLP」を作成できれば、あとはキーワードごとに画像や文章を微調整するだけで、LPの横展開や量産ができるジャンルもあります。
例えば、サプリメントを販売していたとして、「産後太りを解消したい主婦」向けのLPが当たった場合は、そのLPの訴求内容を「運動効率を上げたいビジネスパーソン」向けに少しいじると言うことです。
全てを変えるのではなく、訴求する文言や画像を変更することで、お金をたくさん掛けなくてもLPの量産は可能です!
LP制作は「やってみないとわからない」ものであり、やらないことが最大のリスクです。
まとめ
ランディングページ(LP)は、広告や検索結果からユーザーが「着地するページ」であり、商品購入や資料請求など特定の行動(コンバージョン)を促すことに特化しています。複数の情報を提供するホームページ(HP)が「受けのページ」であるのに対し、LPは1ページで完結し、ユーザーの注意をコンバージョンに集中させる「攻めのページ」です。LPとHPは、目的、構成とページ数、ターゲット、集客方法、デザインの5点で異なりますが、LPにHPの機能を持たせたハイブリッドモデルも可能です。
売れるLPの構築において、最も重要な前提条件は、ユーザーの検索ニーズに合ったLPを作成すること、そしてユーザーを「今すぐ客」と「そのうち客」の二つのパターンに分けてLPを構築することです。
LPの主要な構成要素は以下の通りです:
- ファーストビュー: ユーザーが最初に目にする部分で、わずか3〜10秒で離脱判断されるため、「どんなサービスか」「利用者の暮らしがどう良くなるか」「どう申し込むか」を明確に伝えることが重要です。
- 顧客の悩みに共感する: ユーザーの課題に共感し、その悩みが解決された未来を提示し、実績や権威性で信頼性を高めます。
- 価値やメリットを全て伝える: 提供できる価値やメリット、結果、変化といった情報を全て詰め込み、顧客からの質問が浮かばないほどの情報量が理想です。
- 問い合わせ方法: スムーズな問い合わせを可能にするため、「よくある質問(FAQ)」で不安を解消し、入力フォームを最適化(EFO)し、多様な問い合わせ方法を提供します。明確なCTA(行動喚起)ボタンを最適化し、次の行動へ導くことも不可欠です。
- お客様の声・導入事例・実績: 第三者からの信頼を得るために非常に効果的で、ユーザーの不安を解消し、行動を後押しします。顧客の「属性」を詳しく紹介し、「数値化」して具体的に伝えることがポイントです。
- 選ばれる理由・独自性: 競合にはない「独自性」と「強み」を明確に伝えます。
- 人柄・スタッフ紹介: サービスを提供する「人」の顔を見せることで、安心感と信頼を提供します。スタッフの趣味など個人的な情報を加えることも有効です。
- 動画セクション: テキストだけでは伝わりにくい情報を効率的に伝え、理解度とエンゲージメントを飛躍的に高めます。コンバージョン率が3倍になった事例もあります。
- 価格表記(松竹梅): ユーザーの意思決定を促す「松竹梅の法則」を意識した価格表記が推奨されます。人間が極端な選択を避ける「極端の回避性(ゴルディロックス効果)」を利用し、推奨する「竹」プランに誘導します。
- フッターセクション: 会社概要やプライバシーポリシーなど、購入に直接必要のないリンクはLPの最下部にまとめるべきです。これにより、顧客の購買プロセスを妨げず、Web広告の審査にも通りやすくなります。
- 購入後の流れ: 顧客が購入後に抱く漠然とした不安を解消するため、具体的な「購入後の流れ」を細かく伝えるセクションも有効です。
- リスクリバーサル: 顧客が感じる金銭的、時間的、心理的、身体的などのリスクを売り手側が解消または軽減することで、購買を促進します(例:返金保証)。
LP制作におけるその他重要なポイントとして、以下の点が挙げられます:
- 約8〜9割のユーザーがスマートフォンで検索しているため、必ずスマートフォンの表示で確認すること。
- ゼロから作らず、競合他社の良いLPから要素を「パクる(参考にする)」TTPS(徹底的にパクる)を活用すること。
- プロが作った見栄えの良いLPよりも、素人が情熱を持って作った「ダサいLP」でも十分成果が出る場合があること。
- 1つのLPが当たらなくても、複数のニーズに合わせたLPを量産し、どこかに当たることを狙う「数の暴力」で複数のLPを展開すること。
- LPの文章にはコピーライティング能力が不可欠で、特に「刺さるタイトル」や「限定オファー」を作成することが、ユーザーの興味を引きつけ、購買意欲を高める鍵です。
- LP全体を「ストーリーテリング」で物語形式にすることで、読まれやすいLPが作れ、ビジネスオーナーの「想い」や背景を盛り込むことで、訪問者との感情的なつながりを築き、信頼感や共感を呼び起こすことが可能です。
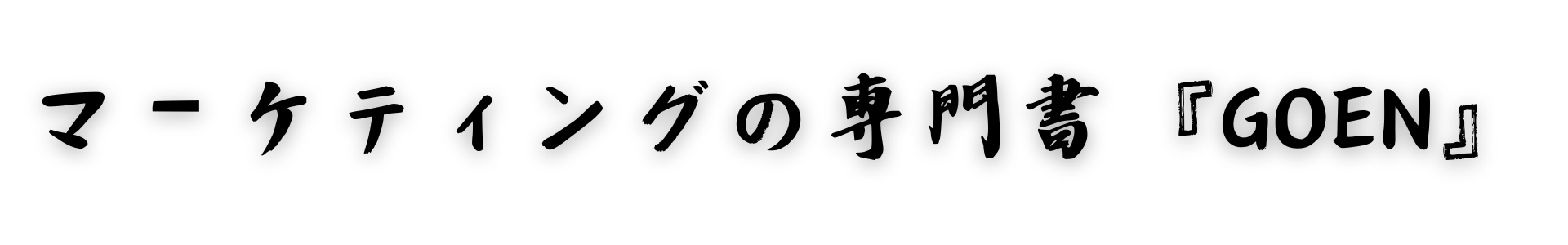
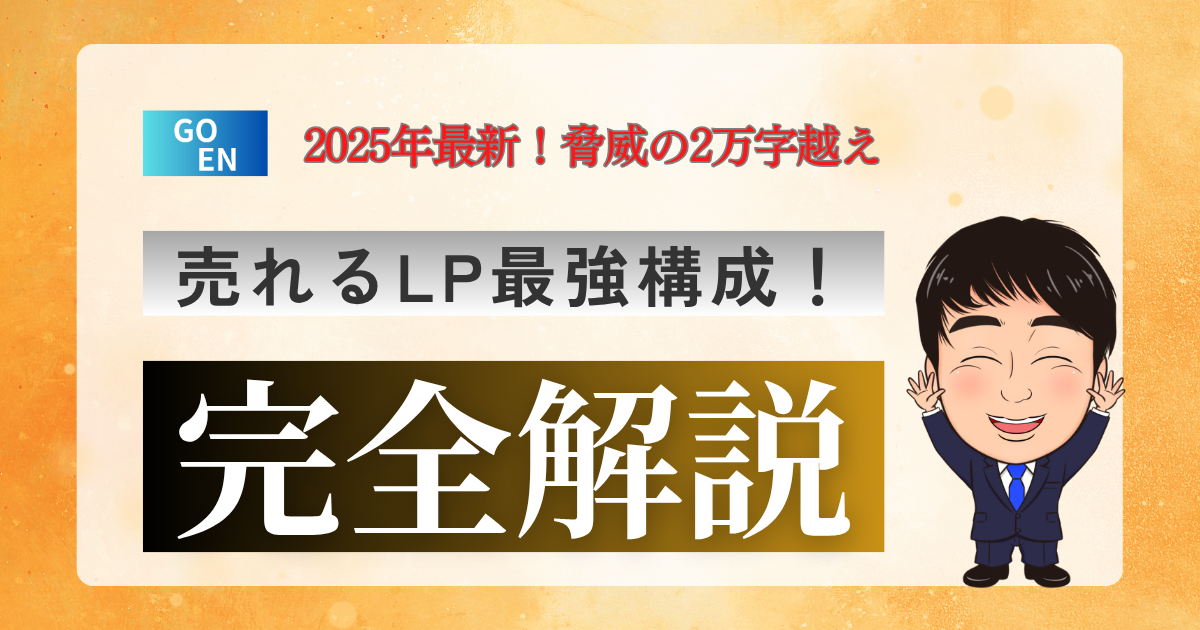
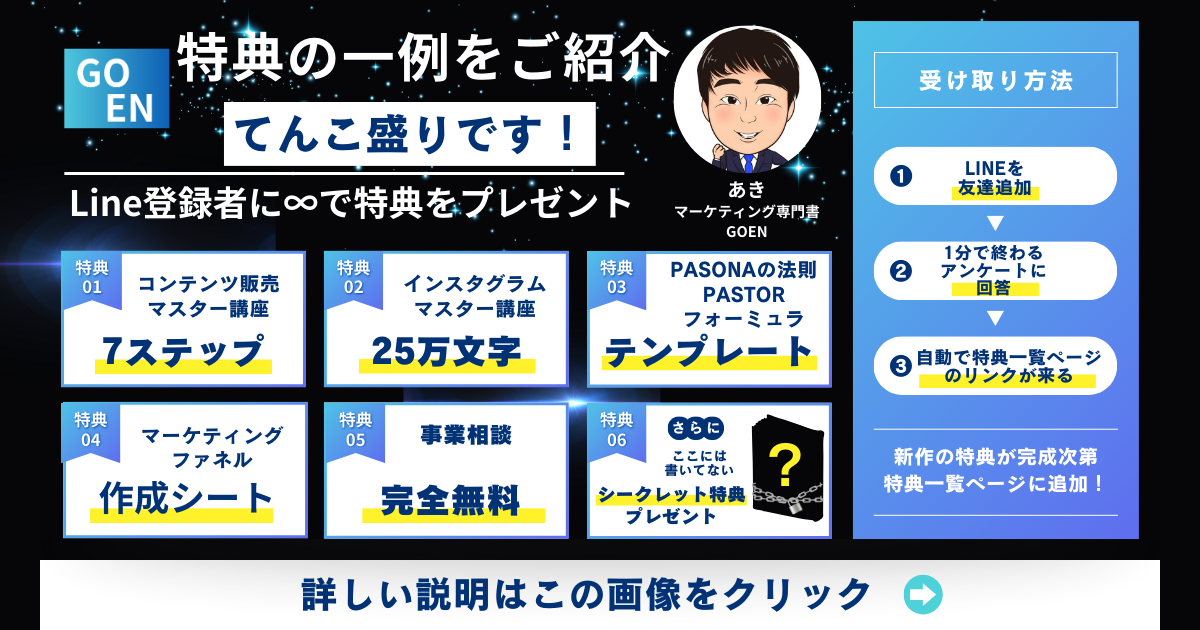


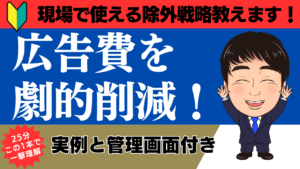






コメント