どうも、あきです。
今回は「Google広告でクリックはされているのに、なぜか売れない…」という方に向けて、除外設定を見直すだけで無駄な広告費を劇的に削減する方法を、実際の事例を交えながら解説していきます。
もしかして、こんな経験ありませんか?
- 「クリックはあるのに、問い合わせがまったく来ない」
- 「アクセスは増えているのに、売上が変わらない」
- 「毎月広告費だけが減っていく」
これらの原因の多くは、除外設定をしていないことにあります。
広告の目的は「クリックされること」ではなく、「買う可能性のある人にだけクリックされること」。
つまり、本当の広告運用とは、クリックされない努力なのです。
この記事では、私が現場で使っている5つの除外設定テクニックを、理論から実践方法まで丁寧に解説します。
読み終える頃には、あなたもきっとこう感じるでしょう。
「クリックは減ったのに、売上は増えた!」
今回の記事の動画はこちら↓チャンネル登録して効率的に広告運用を一緒に学びましょう!
動画の方が記事よりも「例え」を多く入れて話しているので、理解しやすいと思います。
セクション1:除外キーワードの見直し
まず最初に見直すべきは、「どんなキーワードでクリックされているか」です。
多くの人が、「キーワード=広告を出すためのもの」だと思っていますが、実は、どのキーワードを除外するかのほうが10倍大事です。
除外が必要な理由
Google広告の仕組みを簡単におさらいしておきましょう。
あなたが設定したキーワードと、ユーザーが実際に検索した語句が似ている場合、広告は表示されてしまいます。
「フレーズ一致」や「インテントマッチ(部分一致)」では、GoogleのAIが広範囲に関連語句を拾います。
「完全一致」の場合でも、類義語や検索意図が同じと判断されたキーワードでは広告が表示されます。
例えば、あなたが「英語 コーチング」で広告を出したとします。
でも実際には、「英語 独学」「英語 無料 レッスン」「英語 勉強法」など、
明らかに意図の違う検索語句にも広告が表示されます。
つまり、買う気のない人にも広告を見せてしまっているということです。
仮にこれが1クリック200円だったとして、100回クリックされたら2万円。
でも1件も成約しなければ、2万円が丸ごと無駄になります。
このようなことが、実は多くの広告アカウントで日常的に起こっていることなんです。
実例①:英会話スクールでCPAが1/3に
さきほどのオンライン英会話スクールの話をもう少しします。
このクライアントの検索語句レポートを見たところ「英語 無料」「英語 独学」「英語 初心者」「英語 アプリ」など、
無料系や自己学習系の検索ばかりで広告が表示されていました。
なので、これらをすべて除外キーワードに追加。
つまり、「お金を払わない層」には広告を出さないようにしたんです。結果、クリック単価は若干上がりました。
でもCPA(顧客獲得単価)はなんと1/3に改善。広告費を変えずに、成約率が3倍に跳ね上がりました。
除外キーワードは育てるもの
除外キーワードは、一度設定したら終わりではありません。むしろ、運用の中で育てていくものです。
検索語句レポートを毎週チェックし、「これは違うな」「これは興味関心が低いな」というものを少しずつ追加していきます。
たとえば、「無料」「安い」「比較」「口コミ」「ブログ」「体験談」「PDF」など。
これらは情報収集段階のユーザーが多く、購買意欲が低い傾向があります。
そういったキーワードをどんどん除外していくと、徐々に広告の質が上がっていきます。
実践ワーク:あなたの検索語句を診断してみよう
ここで一度、あなたのGoogle広告管理画面を開いてみてください。
1️⃣ 「キーワード」→「検索語句」タブをクリック
2️⃣ 最近1週間のクリックデータを表示
3️⃣ 一覧の中から、自分の理想顧客が検索しそうにないキーワードを探してみましょう
それを一つずつ除外キーワードに追加していくだけで、明日からの配信効率が大きく変わります。
よくある誤解
「除外キーワードを入れすぎると、広告が出なくなりそうで怖い」これ、非常に多い誤解です。
実際には、除外を増やしても配信ボリュームは減りません。
なぜなら、除外するのは本来狙うべきでない層だからです。
むしろ、ターゲットがクリアになって広告のCTR(クリック率)も改善するケースが多いです。
つまり、除外は絞り込みではなく、選別と捉えましょう。
除外キーワードリストの作り方(中級者向け)
ここからは除外の中でもちょっと難しい話をします。
上級者ほどやっているのが、「除外リストを共有資産化」することです。
新しいキャンペーンを作るたびに同じ除外設定をするのは非効率的ですよね。
なので、「除外リスト」を一括で管理して、他のキャンペーンに適用することができます。
- 「無料系ワード除外リスト」
- 「求職者ワード除外リスト」
- 「比較・口コミ除外リスト」
このようにテーマごとに分けて管理しておくと、新しい広告を出稿しても無駄なく配信することができます。
ここに関しては一旦理解できていなくても大丈夫です。
とりあえず、購入に繋がらなそうなキーワードを除外に追加することから始めましょう。
ここまでで「誰に広告を見せるか」を整理してきました。
でももう一つ大事なのが、「どこで広告が見られているか」です。
どんなに良いキーワードでも、表示される場所が間違っていたら台無しです。
次のセクションでは、「除外プレースメント」について詳しく解説していきます。
ここを見直すだけで、広告費の3割が浮くケースも珍しくありません。
セクション2:除外プレースメントの設定
プレースメントとは、広告が表示される「場所」のこと。
特にディスプレイ広告やYouTube広告を出している方は、ここが超重要です。
除外プレースメントのよくある失敗例
「クリック数は多いのに、CVがゼロ…」これ、よくある相談です。
原因を追ってみると、実は場違いなサイトやアプリに広告が出ていた、というケースが圧倒的に多いです。
事例:BtoB企業の広告が無料ゲームアプリに出ていた
私がサポートしたあるBtoBのソフトウェア企業では、クリックの35%が「無料ゲームアプリ」からの流入でした。
しかもCV(成約)はゼロ。つまり、広告費の3分の1が完全にムダになっていました。
この企業ではすぐにプレースメントレポートを開き、「子供向けゲーム」「占いサイト」「まとめ系メディア」などをまとめて除外。
結果、CPAが45%改善し、CV数は2倍に。「無駄を削ったら売上が伸びた」という事例です。
Googleの自動最適化の落とし穴
Googleのディスプレイ広告は、AIが自動で配信先を最適化します。
ただし、初期設定では「クリック率(CTR)」などのエンゲージメント指標を重視して学習が進むため、Googleは「よくクリックされる場所」を良い配信先と判断する傾向があります。
しかし、それが必ずしも「コンバージョンが取れる場所」とは限りません。
結果として、クリック率が高いものの購買意欲が低い、暇つぶしユーザーが多いサイトに表示されやすくなるケースもあります。
典型的な「ムダプレースメント」リスト
- 無料ゲームアプリ
- 占い・診断サイト
- 漫画・エンタメまとめ系
- 無料音楽ダウンロード
- 掲示板系サイト
- 海外ニュースや翻訳まとめ
こうした媒体はクリックはされやすいものの、購買・問い合わせに繋がりにくい傾向があります。
YouTube広告の場合も同じ
プレースメントの考え方はYouTube広告にもそのまま当てはまります。
たとえば、あなたがBtoBのサービスを扱っているのに、広告が「アニメの切り抜き動画」や「子供向けコンテンツ」に出ていたら、どんなにクリック率が高くても意味がありません。
YouTubeでも「コンテンツテーマの除外」が可能です
- 子供向けコンテンツ
- エンタメ・アニメ
- ゲーム実況系
- 暴力的またはショッキングな内容
- 成人向け
これらを除外しておくだけで、視聴の質がグッと高まります。
逆に残すべきプレースメントとは?
除外ばかりではありません。残す判断も大切です。
たとえば、以下のようなメディアは質が高い傾向があります。
- 業界ニュースメディア
- 専門情報サイト
- レビューサイト(公式・専門家系)
- 関連業種のYouTubeチャンネル
ここを見極める力が、広告運用のプロと素人の大きな差になります。
ここまでで、「誰に」「どこで」広告を見せるかという2つの軸が整理できました。
次に見直すべきは、「どの地域で広告を出すか」。意外とここを放置している人が多いんですが、地域設定を間違えるだけで広告費の半分がムダになるケースもあります。
次のセクションでは、「除外地域の設定」をテーマに、具体的な事例と設定ポイントを解説していきます。
セクション3:除外地域の設定
実はこの地域設定、成果に直結するのに分からないで設定していない方がたまにいます。
地域の設定は必ず確認しておいてほしい項目です。
特に店舗系の方は必ずお店から半径何キロ以内みたいな設定をしておいた方がいいでしょう。
除外地域の設定のよくある間違い
たとえば、あなたが東京にある整体院を経営しているとしましょう。
「東京 整体」というキーワードで広告を出しているとします。
一見、ちゃんと地域を絞っているように見えますよね?でも、実際に広告の表示地域をレポートで確認してみると「大阪」「札幌」「福岡」「沖縄」などでも広告が出ている。
えっ?なんで?と思うかもしれませんが、これはGoogle広告の仕様上、初期設定のままだと全国配信されるからなんです。
広告を少しでも理解している方なら、そんな人いるの?って思うかもしれませんが、実際に無料相談に来た方でそのような方がいました。
Google広告「地域ターゲティング」の意外な落とし穴
Google広告の地域設定には、2つのモードがあります。
1️⃣ 「その地域に実際にいる人に広告を出す」
2️⃣ 「その地域に関心を持っている人にも広告を出す」
多くの広告アカウントでは、デフォルトでこの2番目──「関心を持っている人」も含まれる設定になっています。
つまり、「東京 整体 行きたい」と検索した北海道のユーザーにも広告が表示されてしまうのです。
その結果、実際には来店できない人や購入できない人にも広告が配信され、無駄なインプレッションやクリックが発生してしまいます。
実例:歯科クリニックが広告費40%削減に成功
ある東京都内の歯科クリニックでは、広告が全国に配信されており、遠方からのクリックが全体の30%を占めていました。
地域を「東京都・神奈川県」だけに絞り、他の地域を除外したところ
- 広告費:40%削減
- 問い合わせ件数:2倍に増加
クリック数は減りましたが、無駄クリックが消えたことで利益が大幅アップしました。
地域設定で売れる構造を作る考え方
このように除外地域を設定すると、「配信対象人口が減って広告のリーチが減るのではないかと不安になる方がいますが、それは逆です。
広告は広げることではなく、絞ることで強くなる。あなたの商品・サービスが届く範囲を明確にし、「どこに売らないか」を決めましょう。
ここまでで「地域のムダ配信」を止めることができました。
次に見直すべきは、どんなデバイスで広告が見られているかです。
多くの人が設定を初期のままにしていますが、ここもチェックしておくと広告精度が上がります。ただし、正直に言って今ままで紹介したものよりは重要度は低いです。
セクション4:除外デバイスの見直し
Google広告では、デバイス別に配信を細かく制御できるため、ターゲット層に合わせた最適化が可能です。例えば、「スマホ」「PC」「タブレット」それぞれのデバイスに対して、配信の有無や入札調整を調整できます。
ほとんどのアカウントは初期設定のままで、すべてのデバイスに均等に配信していることが多いですが、これが成果を阻害している場合もあります。例えば、モバイルに最適化したサイトや商品を持つ場合は、スマホに重点的に入札を高めることで効果を最大化できます。一方、詳細な情報や申込みがPCから多い場合は、PCの入札を強化すると良いでしょう。
設定方法もシンプルで、Google広告の管理画面から「デバイス」を選び、それぞれの調整比率を変更します。調整幅は-100%から+900%まで設定でき、実際の配信目的や流入データに基づいて最適化を進めるだけです。
このように、多くの企業は初期設定のままで済ませてしまい、むしろ成果の最大化を妨げているケースもあります。デバイスごとの配信比率を適切に調整することで、無駄な予算消費を防ぎ、より効率的な広告運用が実現します。
実例①:ITコンサル会社がCPAを半減させた事例
あるBtoBのITコンサル企業。スマホからのクリック率は高かったのに、コンバージョン率は0.5%。
一方で、PCはクリック率は低いけどCV率が3%。つまり、スマホクリックの大半が無駄だったんです。
思い切って、スマホ入札を −80% に調整し、その分、PCの入札を +50% に引き上げ。
結果、クリック数は減ったものの、CPAは半分以下に改善。「数」より「質」を選んだ成功例です。
ここまでで、
- 誰に見せるか(キーワード)
- どこで見せるか(プレースメント)
- どの地域に出すか(地域設定)
- どのデバイスで見せるか(デバイス調整)
という4つの除外を見直してきました。
残る最後の要素は──「誰に見せないか」。
つまり、オーディエンス(属性や興味関心)を除外するという考え方です。
ここが一番、成果を左右します。
セクション5:除外オーディエンスの活用
ここまでで「キーワード」「場所」「地域」「デバイス」を最適化してきました。
つまり、広告が出る条件を整えたわけです。
最後に見直すべきは、誰に広告を見せるかの中身、つまり、オーディエンスです。
オーディエンスとは?
Google広告におけるオーディエンスとは、ユーザーの行動履歴や興味関心、年齢層などの属性情報をもとにGoogleが自動で作成する「属性データグループ」のことです。具体的には、「過去に自社サイトを訪れた人」「特定の興味・関心を持つ人」「購買意欲の高い層」「既存顧客」などがオーディエンスとして定義されています。
オーディエンスを活用することで、広告は買わない層を外して、買う可能性の高い層だけに配信するという高度なターゲティングが実現可能です。また、Google広告にはアフィニティ(興味関心)、ライフイベント(結婚・引越しなど)、購入意向の強いユーザー層や、過去に自社サイトを訪問したユーザーを含むリマーケティングのオーディエンスなど、多様な種類があります。
これらを正しく使い分けることで、買わない層を外し、買う層だけに見せるという戦略が可能になります。
なぜ除外オーディエンスが重要なのか?
Google広告は、設定していない限り、誰にでも広告を出そうとします。
AIが「広く学習」しようとするため、意図しない層にも配信されがちです。
だからこそ、配信してはいけない人を最初に明確にしておく必要があります。
これが「除外オーディエンス戦略」です。
除外すべき代表的なオーディエンス層
- すでに購入済み・問い合わせ済みの人
- 明らかにターゲット外(10代・学生など)これは商材による
- 興味カテゴリがズレている層(例:ビジネス商材なのに「エンタメ・アニメ」興味)
- 何度もクリックするのにコンバージョンしない人
これらは除外すべきオーディエンスと言えます。
実例:ECショップでリマーケティング地獄から脱出
あるECサイトでは、リマーケティング広告を運用していました。でも、購買済みユーザーにも広告が出続けていたんです。
結果として、一度買った人が何度も広告をクリックし、広告費を浪費。そこで、「購入済みユーザー」を除外リストに追加しただけで
広告費が20%削減され、ROAS(広告費対効果)は1.8倍に上がりました。「配信しない勇気」が利益を生む事例です。
除外オーディエンス設定の3ステップ
1️⃣ すでに購入や問い合わせを完了したユーザーを除外することから始めます。これにはコンバージョンタグや顧客リストを利用して、既存顧客への無駄な広告配信を防ぎます。
2️⃣ 次に、オーディエンスの興味・関心カテゴリを精査します。例えば、「アニメ」「ゲーム」「恋愛」など、ビジネスと関連しないカテゴリを除外することで、よりターゲットに近い層に絞り込めます。
3️⃣ 除外設定は一定期間ごと(30日・60日・90日など)に見直して更新します。これにより、広告配信の最適化を維持しつつ、「除外設定が複数回適用されている層」への過剰な除外を防ぎ、効率を高めることができます。
除外しすぎの注意点
除外オーディエンスを設定しすぎると、配信ボリュームが急に減ることがあります。
特にリマーケティングやターゲティング広告では、「広告が出ない」状態になるリスクも考えられます。
そのため、段階的にテストするのがおすすめです
1回目:広めに配信
↓
2回目:成果が悪い層を除外
↓
3回目:優良層だけを残す
この「絞り込みサイクル」を回すことで、広告はどんどん強くなります。
このチャンネルで何度か言ってますが、このようなサイクルがあるので、広告は短期決戦ではないのです。
現場でよく使われる除外リストの型
実際に広告代理店で使われている除外リストの一例をご紹介します。
| リスト名 | 内容 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 購入済みユーザー除外 | コンバージョン済み顧客 | 180日 |
| 問い合わせ済み除外 | 問い合わせフォーム送信者 | 90日 |
| サイト滞在0秒除外 | 直帰ユーザー(即離脱) | 30日 |
| 興味関心ズレ除外 | アニメ・ゲーム・趣味カテゴリ | 常時 |
これをキャンペーン全体に適用しておくだけで、
ムダクリックの大部分が消えます。
ここまでのまとめ(セクション1〜セクション5)
ここまで見てきた除外設定を整理すると
| 項目 | 除外する対象 | 主な効果 |
|---|---|---|
| キーワード | 無料・比較・口コミなど | 無駄クリック削減 |
| プレースメント | ゲーム・まとめサイト | 成約率アップ |
| 地域 | 成果の薄いエリア | 広告費効率化 |
| デバイス | 成果の出ない端末 | CPA改善 |
| オーディエンス | 買わない層・既存客 | ROAS向上 |
これらを1つずつ丁寧に見直すだけでも効果は出ます。
でも、本当の力は組み合わせにあります。
ここまでの5つの除外設定、1つだけ実践しても成果は上がります。
しかし、真の成果は掛け合わせにあります。
次のセクション6では、これらの除外設定をどう連動させるか、
そして、広告費を最大限に活かす「除外設計の地図」を一緒に描いていきましょう。
セクション6:除外設定の掛け合わせ戦略
ここからは、少し上級者向けの内容となります。
でも、この考え方を理解すれば、あなたの広告運用は確実にワンランク上に行くはずです。
広告は「誰に見せるか」より、「誰に見せないか」で決まる
多くの広告運用者は、見せる努力ばかりしています。
でも、本当に成果を出している方は、見せない努力をしている。
たとえば私が過去に運用したクライアントで、1年でCPAを60%改善した会社がありました。
その成功要因はたった1つ。「除外設計を仕組み化した」ことです。
除外設計の3レイヤー構造
除外設定を体系的に理解しやすくするために、3つのレイヤー構造で考えることをおすすめします。
まず、レイヤー1は「検索意図の除外」です。ここではキーワード単位で、無料、口コミ、比較、安い、体験談など、購買に関係ない検索意図を除外します。これにより、無関係な検索ユーザーをフィルタリングできます。
次に、レイヤー2は「環境の除外」です。広告が表示される位置(プレースメント)、地域、デバイスなどの配信環境を見直し、配信先や条件を最適化します。これにより、広告が不適切な場所や対象外の地域・端末で無駄に露出することを防ぎます。
最後に、レイヤー3は「属性の除外」です。ここで買わないユーザー層、既存顧客、興味関心が合わないオーディエンスを除外します。こうしたターゲット属性の精査により、広告の効率をさらに高められます。
この3つのレイヤーを総合的に管理することで、「誰に・どこで・どんな状況で」広告を配信するかが明確になり、無駄のない効果的な広告運用が可能となります。
実例:広告費を半分にして売上を1.8倍にしたBtoB企業
あるBtoB企業では、広告費100万円で月10件の問い合わせ。
しかし除外設定を強化した結果
- 広告費:50万円
- 問い合わせ数:18件
という結果に。実施したことはシンプル。
1️⃣ 「転職」「求人」「年収」などのキーワードを除外
2️⃣ スマホ入札を−70%
3️⃣ 地方エリアをすべて除外
4️⃣ オーディエンスで学生層を排除
これらを連動させることで、本当に買う人だけに届く広告が完成しました。
除外は「守り」ではなく「攻め」
最後に強調しておきたいのは、除外設定は守りの施策ではなく、攻めの施策だということです。
クリックを減らすのではなく、利益を最大化するために無駄を削るという発想です。
つまり、「削る」=「伸ばす」。
この感覚を持つと、広告運用が一気に変わります。
まとめ
1️⃣ 除外キーワードで無駄な検索を削り、ターゲットを明確化する
2️⃣ 除外プレースメントで場違いなサイトを外す
3️⃣ 除外地域で成果の薄いエリアを切る
4️⃣ 除外デバイスで無駄なクリックを防ぐ
5️⃣ 除外オーディエンスで買わない層を外す
6️⃣ 掛け合わせ設計で広告費の無駄をゼロに近づける
広告は「どれだけ見せるか」ではなく、誰に見せないかを決めることで成果が変わります!
最後に伝えたいこと
除外設定は、ある意味「マーケターの意思表示」です。
「うちはこの人たちには売らない」その覚悟があるからこそ、本当に買ってくれる人に届く。
だから、怖がらずに一歩ずつ削っていってください。
1週間後、あなたのGoogle広告の数字はきっと変わっています。
クリックは減るかもしれません。でも、売上は上がります。
もし「自社ではどうすればいい?」と感じたら
もし「自社の業種ではどこを除外すべきか?」
「優先順位を教えてほしい」などの疑問があれば、お問い合わせから無料相談を受け付けています。
実際のアカウントを見ながら、業種ごとの最適な除外戦略をお伝えします。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
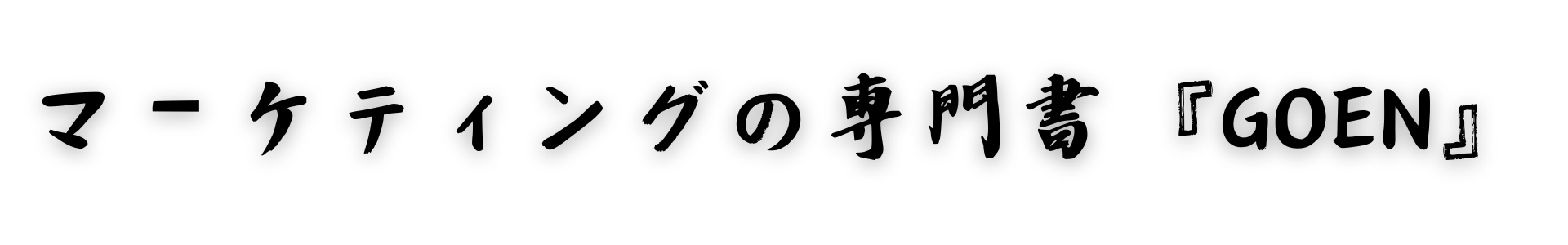
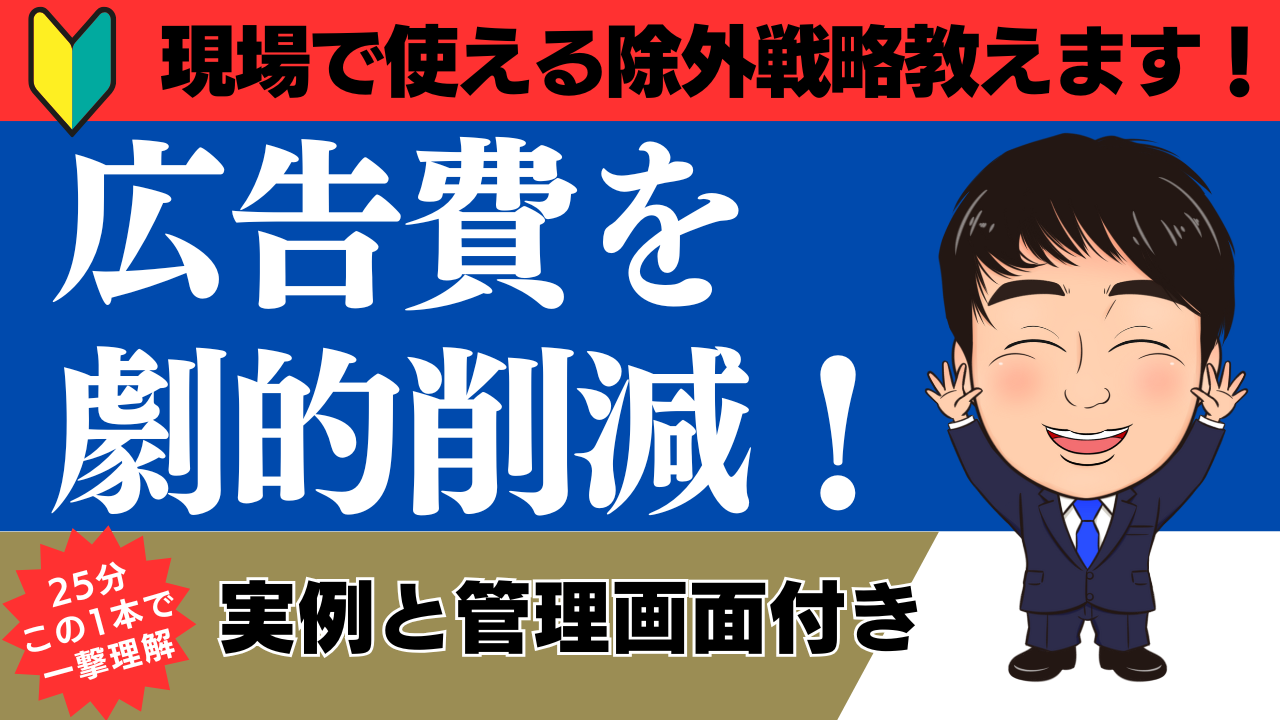





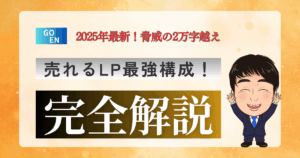
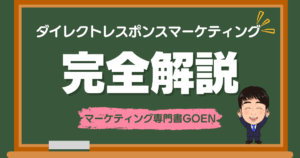

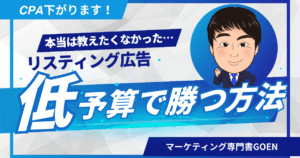
コメント